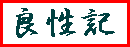
18歳未満の方は入場をご遠慮下さい。
適格退職年金から移行の話
平成13年4月に、私はP社からS社に出向しました。
新しい職場で、書類を眺めてS社の社内ルールを子細に確認しました。そこで私は幹部の誰もが気づいていない重大問題があることに驚きました。
それは、S社の退職年金が大変困った内容になっていたことでした。
何に困ったかと言うと次の二つです。
1.給付額の不合理性の問題
S社の退職年金は適格退職年金制度によっていた。その適格退職年金制度は勤続年数だけを退職年金額の決定要素にしており、その結果、退職金の額があまりにも平等的でありすぎるものであった。
具体的には次の不具合が認められた。
(1) 勤続年数の長い者が単純に有利な給付を受ける。
高卒18歳で入社して42年間勤続した者〜退職年金の一時金評価額…27百万円
大卒22歳で入社して38年間勤続した者〜退職年金の一時金評価額…20百万円
☆ たとえば、55歳到達、若しくは、勤続33年経過で退職金の上昇をストップするというような合理的な考えが織り込まれていないから、このような不具合が生じた。
(2) 退職者の会社に対する貢献度が、退職金の算定に当たって考慮されていない。
部長や課長職の経験者に、より厚く退職年金を給付することが全くない。
(3) 最終職位から見て給付額が立派すぎることが起こりえた。
企業には、総合職(企画職、主務職)と執務職(一般職、事務職)というような役割の区分があり、たとえば高卒の女子社員で補助的な仕事をやっている人、これは執務職に該当する。
それで、S社の適格退職年金制度によれば、高卒で執務職から総合職へ転換して、たとえば課長代理までは昇進できなかった人や、高卒で執務職のまま定年を向かえた人が、高卒で部長や課長までも務めた人と同額の退職金27百万円の給付を受けることになる。
(これが、大卒の入社であれば勤続年数が短くなり、20百万円の給付になるから、これを上回ることになる)
この27百万円という支給額があまりにも高い。
(その者が部長経験者ならば高い金額ではないかもしれないが…)
S社の親会社であるP社では、高卒で課長代理クラスで定年を迎えた男性は20百万円ぐらい、高卒で執務職のまま定年を向かえた女性は15百万円ぐらい、これが60歳定年退職の場合の金額だった。
これに対してS社の給付
(18歳で入社の者は27百万円)はとんでもないほど立派すぎて、それでは子会社として、親会社に対して説明がしにくい状態である。
(幸いにして、S社は創立20年程度で、定年退職者が出るのはまだ先だから、退職金制度の改訂は間に合う。それにしても、生保会社の提案商品に単細胞的に追従しすぎであった!)
(4) 途中入社の者の退職金が少なくなりすぎる。
(1) の通り、高卒者と大卒者とでは最後の在籍期間の4年の違いで支給額に7百万円の差がある。
一方、早い時期での退職、3年在籍した者と7年在籍した者とでは、同じ4年の違いでも、退職金の差が40万円程度にとどまっている。(退職金の額:3年…20万円、7年…60万円)
ということは、在籍が長くなればなるほど、支給額が急カーブで上昇することを意味する。
すると、たとえば35歳で途中入社した者、これは、有能な者をキャッチして部長職にまで登用した場合でも、この人の勤続年数が短いだけに退職金がかなり淋しい金額になってしまう。
(優秀な人をスカウトしにくく、ダメな社員に退職決意を生じさせにくくしている)
2.運用利回りから発生する問題
S社の適格退職年金制度は20年前からQ生命保険社に委託してあった。
予定運用利回りは5.5%で設計してあり、現実の運用利回りとの差が拡がっていることが重大な問題であった。
(1はS社の適格退職年金における固有の問題だとも言えるが、2は企業年金全体の問題である)
具体的に数値を見ると次の通り。
| 毎月の掛け金 |
PMT(年利/12,年数×12,0,要積立額,1)
※月利と月数とにレベルが合わせてある |
| 12,950円 |
PMT(5.5%/12,38×12,0,20000000,1) |
| 26,264円 |
PMT(2.5%/12,38×12,0,20000000,1) |
| 32,527円 |
PMT(1.5%/12,38×12,0,20000000,1) |
22歳入社で38年勤続した者が退職金を20百万円受け取るためには、会社は毎月いくら掛け金を支払うべきかをExcelの関数PMTで計算したのがこの表です。
これからわかることは、20百万円を積み立てるために、
利回りが5.5%ならば毎月12千円
利回りが1.5%ならば毎月32千円
の掛け金を支払うことです。随分差がありますね。
現実の運用利回りが、日本経済の失速によって、計画の5.5%よりはほど遠い
1.5%しかないならば、後追いの追加掛け金として莫大な金額が必要になるということがよく理解できます。
その積立不足額が、従業員数一人当たりで 170万円に達していました。すごい借財です。
(適格退職年金制度に限らず、企業年金を導入している会社は、すべてこれぐらいの金額を下限とする借財があると思って下さい。とても恐ろしいことです。社員千人の会社であれば17億円、社員1万人の会社であれば170億円、という巨額の積立不足です)
この大きな問題を社長に説明すると、社長は大変驚きました。
私はすぐにS社の退職金規定を再構築することにかかりました。
いろいろ思案して、結論は、Q生命保険社に委託してある適格退職年金制度を、公の機関が運営している『中小企業退職金共済制度(中退共)』に乗り換えることでした。
結果的にこれは成功し、適格退職年金の積立額の殆どを中退共に移すことが図れたけれど、途中過程ではなかなか難しいものがありました。
とにかく、労働者の既得権の縮小はやってはならないという理屈で、こちらの思惑がなかなか通らなかったのです。
それはそうです。私の気持ちは、
(1) 課長職などに至らなかった定年退職者(42年勤続)に27百万円を払うという規定はかなわん。
(2) 『功績対応』の考えを退職金に入れ込みたい。
(3) 途中入社の人が大きく不利にならないようにしたい。
の三点ですから。
この修正を加えたい以上、社員の中には将来得べかりし既得権が縮減される立場の人も必ずいるわけで(たとえば、高卒で課長職にまでならなかったような人)、そうなると法律の規制?からなかなか思惑通りにはいかなくなります。
その点中退共は国の推奨?する制度だから、あまり制約なく(従業員の賛同が不要…これが重要)適格退職年金制度から移ることができます。
企業年金の法制度の充実化により、これまでの適格退職年金制度は10年の猶予期間をおいて廃止されることになっています。
仮に、適格退職年金から、中退共ではなくて、確定給付年金や確定拠出年金に移行することにすると、従前の適格退職年金制度の、素晴らしきほどに『公平な』規定での支給を維持して、社員の既得権が犯されないように、新しい企業年金制度を構築して、これに移行しなければなりません。
高卒の42年勤続者であろうが、課長職にまで到達しなかった者であろうが、既存の適格退職年金制度での給付を下回らないようにして新企業年金を設計するのであれば、事実上私が問題視したことが解決できません。
企業年金制度の改変は従業員保護の観点から、給付が増加する改訂は差し支えないけれど、減少する人が発生する改訂はいかなる理屈があろうと現実には許されません。これが許されるのはそれこそつぶれそうな会社だけです。
一方、各企業は、10年も20年も前に構築した退職金の規定は、経営環境が様変わりした今、給付額を総額としてダウンさせる方向へ持ち込みたいです。従来の規定のままでは、企業は退職金で倒産します。
中退共には、適格退職年金の骨子(素晴らしき平等主義)を事実上ご破算にして移行ができました。
中退共に支払う(個人毎の)掛け金を、適格退職年金の時のものよりも引き上げさえすれば、退職時の給付額が落ちるのを無条件で許されるのです。支給額が落とせるのも掛け金負担が増えるのも、経営側から見れば大歓迎です。
掛け金を引き上げて『費用として処理できる』金額が増額するのは、収益力のある会社ならば結構なことです。更に、移行によって給付の仕組みをより合理的に変えることができました。超理想主義的悪平等・超博愛主義的給付とおさらばができました。
両者の概要は次の通りです。
|
毎月の掛け金
(一人当たり) |
年間の掛け金総額 |
22歳大卒入社が38年勤続の場合の支給額 |
| Q生命保険社 |
12千円 |
12百万円 |
20百万円 |
| 中退共 |
12〜28千円
(注1)
(平均19千円) |
20百万円 |
平均的に10百万円
(注2) |
(注1)12〜28千円とは、役職等によって掛金に差をつけたから。
(執務職:月額12千円 部長職:月額28千円)
(注2)平均的に10百万円とは、役職等によって然るべく給付差をつけたということ。
(8百万円〜12百万円)
掛け金の支払額が年間で12百万円→20百万円と増えました。にもかからわず上の表の退職時支払額が20百万円→平均10百万円 と減少しています。
何故でしょう。
それは適格退職年金が5.5%、中退共が約1%と利回りに大きな差があるからです。しかし、残念ながら後者の利回りが現状にはマッチしています。
適格退職年金では大きな“積立不足額”を抱えているのに対し、中退共ではそれが解消し、その代わり、給付額が半減しています。
社員の退職時に、中退共からは平均10百万円しか出ないので、定年退職時には会社からの上乗せ支給が必要です。適格退職年金の“積立不足額”が解消した代わりに支給できる退職金が減っています。
主任・課長代理クラスよりも上の者については、定年退職の退職金を最低でも20百万円支給すると決めれば、会社が追加で支払う一時金は10百万円以上の金額となります。
この退職一時金を、本人の功績に応じて決定すればよいということになります。
従業員から見れば、会社が毎年外部に払う金額が、12百万円→20百万円と増えるのは大変結構です。会社が引き出しすることのできない外部積立なので、少なくともこの部分については、(懲戒解雇でない限り)個人別に受給権が確定すると言ってもいいのですから。
会社は毎年20百万円を中退共に支払います。20百万円が概ね定年退職者一人あたりの退職金額とするなら、10年で10人分の退職金額が会社の外に蓄えられるわけです。
従業員にとってハッピー、会社にとっても、将来必ず必要になる費用をあらかじめ先落としすることができて、健全なオペレーションになります。
なお、細かいことを付け加えれば、通常、退職金制度には『自己都合退職修正係数』というのを織り込み、たとえば勤続10年未満の退職の場合は支給額を50%に減額するようなことをしています。
しかし、中退共の制度を使えば、自己都合退職の場合の給付減額ができません。
ですから、掛け金が年額12万円(月額1万円)と決めれば、退職金は勤務年数1年あたり12万円強となり、たとえば10年働いて結婚退職する女性に対しては 120万円以上の金額の支給となります。
自己都合の退職の場合は金額をへらすという規定には、したくてもできません。
手元に『図解・小さな会社の退職金の払い方』(東洋経済新報社)という本があります。
ここに私が経験したのと同じケースが書かれているから紹介します。
適格年金の問題を考えるときに、どうしても避けて通ることができないのは給付の減額です。これまでに説明してきたとおり、金利の低下は重大な影響を与えています。(中略)掛け金の増額とともに、当然給付の削減も行うべきですが、ところがそれが難しいのです。
適格年金はそれを始めるには国税庁長官の承認が必要で、その給付の減額に関しても承認するかどうかという権限を持っています。生保会社や信託銀行はこの国税庁の顔色をうかがいながら申請業務をしているわけです。(中略)
この中(注:国税庁の意向の文書)には「給付の減額は、相当の事由のある場合を除いて、原則として認められない」と明記されています。問題はその「相当の事由」の内容です。(中略)「運用利回り等の著しい低下等の事由により過去勤務債務等の額が著しく増加し、給付の額を減額しなければ掛け金等の払い込みが困難になると見込まれるため、給付の額を減額する場合」は 「相当の事由」に該当するようです。
しかし、実際には減額が認められることはまれなようです。このため適格年金を解約する事業主が全国で急増しています。適格年金は給付の減額は難しいのですが、解約は事業主のハンコ一つで簡単にできるため解約に至っているのです。そのときはたまった原資が従業員に直接分配されるだけで、企業側は過去勤務債務の償却を求められることはありません。しかし、もしも解約してしまったら、従業員にとってはそれが一番不利益なことであり、元も子もなくなってしまいます。(中略)
適格年金は、その運用利回りが5.5%だったものが、低金利が続く今日の状況を考えますと、十分「運用利回り等の著しい低下」といえると思います。では給付の減額を認めてくれるのかといいますと、実際のところはそうでもないのです。実際には生保会社側が自主規制をしているせいか、あるいは国税庁当局が給付減額に対して厳しい姿勢を崩していないせいか、本当の原因は不明ですが、給付減額に関してはいまでも事実上「NO」になっているのです。
また、生保会社の対応にも疑問があります。(中略)他の生保会社は「給付減額は認められない」の一点張りでした。なぜ給付減額ができないのか、その説明をしようともしません。私が「給付減額に関する国税庁長官通達」まで出して、説明を求めますと「本社に問い合わせてみます」と言って逃げてしまい、それっきりです。要するに「面倒なことは御免だ」という生保会社側の姿勢をみたような気がします。
私に言わせれば、国税庁もおかしければ、生保会社もおかしいと思います。いま中小企業の経営者は「低金利」という問題に直面していますが、そもそも低金利という問題は事業主に責任があることですか? 日本の金利がこれだけ短期間で下がることを誰が想像し得たでしょうか? 誰にも予期しえぬ事態であるはずです。それにもかかわらず、低金利のシワ寄せをなぜ事業主だけが一方的に負わねばならないのか理不尽すぎます。こんなことでは中小企業が本当に退職金倒産してしまいます。
恣意性の排除という考えから、企業年金制度の適用が厳しいがために、適格年金を解約するケースが増えているというのは大変な問題です。
それにしてもこの記述は私が大いに頷けるものです。
私も生保会社にこのような応対をされました。壁にぶち当たった気分でした。
自分が管理責任を持つ会社の適格年金において
高卒女子が(勤続年数の違いにより)大卒の部長職を退職金で凌ぐような制度は親会社に説明できない。
5.5%の利回りによる年金額の設計はもう現実的ではない。
この二点をQ生命保険社の支店長クラスの人にお願いしても、それこそクソミソの応対をされました。
「お宅の会社の退職金規定は労働者の権利保護、平等をそのまま規定したような、他社の模範となる規定です。これを一時の社長や人事責任者がご自分の考えでころっと変えたいと希望するのは大変良くないことでしょう」
というような高圧的な姿勢です。こちらが「お客」なのに、まいりました。
債務超過に陥っているような会社でない限り退職金の切り下げに当たるような変更をすることはできないという説明でした。それでは、健全な経営状況にある会社は、デフレ環境に合わせた退職金の是正が金輪際できません。
しかし、中退共への移行という便利な手がありました。これならば、事実上の年金引き下げができました。(言いかえれば、5.5%の非現実的骨格から、1%の現実への転換)
まあ、2年かかってようやく最適な移行ができました。大変苦労しました。
更に、余談です。
適格退職年金から中退共への移行というのは、実質的には退職金の切り下げになります。だから、会社からの一時金給付を追加することをやったほうがいいです。
現在、全国で、多くの中小企業が中退共への移換えを検討しています。ところが、これがなかなかうまくいきません。大変時間がかかっているのです。
私の会社では、適格退職年金の脱会から中退共への加入を、わずか一ヶ月で行いました。中退共の窓口の人の説明によれば、これはかなり珍しいことだそうです。
中退共への移行や新企業年金への切り替えがどの企業も大変もたもたしているのは、次が理由と考えられます。
(1) 実質的な年金給付の切り下げを敢行するリーダーシップが企業の人事部門にない。
(2) 年金給付の切り下げを緩和し、成果主義を取り入れた一時金給付について検討が不足している。
(3) この二つにより、人事担当者が『自分の不利益になること』をしたがらない。
退職金制度の決め方なんて何通りでもあります。だから、権限のある人が勇気を持って決める必要があります。
ところが、現実的には、適格退職年金から中退共への移行というものでも、企業はすぐ専門家に頼ります。『社会保険労務士』なんかに仕組みづくりを依頼するんですねえ。
すると、委託費用は2、3百万円になります。部長が方向付けをしっかり行い、担当者がEXCELを操作すれば、シミュレーションも設計もすぐにできます。社会保険労務士に依頼する必要は全くありません。
中退共のサイトをよく見て、考えれば、何をどうしたらよいかはすぐに判断できます。わからないことは係の人に聞けばいい。
それに、退職金の切り下げは、早くやっておかないとますます厄介になりますよ。第一次ベビーブーマーがそろそろ退職時期を迎えます。そして、脱会が遅延すれば遅延するほど、適年を委託している金融機関から積立不足額の追加拠出を依頼されてしまいます。
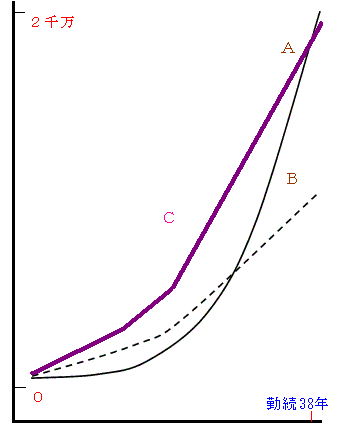 縦軸が退職年金の一時金評価額で、横軸が勤続年数です。取りあえず、縦軸は2千万円を上限値とし、横軸は大卒22歳入社・60歳定年・38年勤続を上限とします。
縦軸が退職年金の一時金評価額で、横軸が勤続年数です。取りあえず、縦軸は2千万円を上限値とし、横軸は大卒22歳入社・60歳定年・38年勤続を上限とします。
これでもって、掛金が定額の場合の退職金のグラフを示します。
曲線Aが運用利回り5.5%で設計した場合の支給額のカーブで、これくらいの利率ですと当然急速に右上がりです。これは入社2年目も35年目も毎月の掛金が同額としても、これぐらいの右上がりのカーブとなります。
曲線Bは運用利回り1%で設計した場合の支給額のカーブで、殆ど直線的です。
曲線Aが相対的に少額の掛金で、38年後の2千万円支給を果たすのに対して、曲線Bは高額の掛け金をセットしてもなかなか1千万円給付に達することが難しいです。
曲線Cは「初め〜掛金を低く、職位が上がると〜掛金を高く」という運用をして、運用利回りが1%でもなんとか2千万円を支給しようとするグラフです。
問題は、曲線Cが実務的に可能かということです。
運用利回り1%というのは、ゼロ金利と殆ど同じですね。掛金のモデルを2つのケースで設定して、金利ゼロにて試算して見ましょう。
| ケース1 |
ケース2 |
| 資格 |
月掛金 |
年掛金 |
資格在籍年数 |
掛金総額 |
資格 |
月掛金 |
年掛金 |
資格在籍年数 |
掛金総額 |
| 見習い期間 |
− |
− |
1年 |
− |
見習い期間 |
− |
− |
1年 |
− |
| 甲 |
1万円 |
12.0万円 |
9年 |
108万円 |
甲 |
2万円 |
24.0万円 |
9年 |
216万円 |
| 乙 |
2万円 |
24.0万円 |
5年 |
120万円 |
乙 |
3万円 |
30.0万円 |
5年 |
150万円 |
| 丙 |
2.5万円 |
30.0万円 |
10年 |
300万円 |
丙 |
4.5万円 |
54.0万円 |
10年 |
540万円 |
| 丁 |
3.5万円 |
42.0万円 |
13年 |
546万円 |
丁 |
6.5万円 |
78.0万円 |
13年 |
1,014万円 |
| 合計 |
|
|
38年 |
1,074万円 |
合計 |
|
|
38年 |
1,920万円 |
ケース2はケース1に対して、スタートの掛け金月額を二倍の2万円にして、更に、資格・役職が「丁」に至った時には掛け金月額を6.5万円と相当の高額にまで引き上げています。こうやってケース2で退職金がようやく2千万円近くになるのに対して、ケース1では1千万円程度にしかなりません。
となると、ケース2で実施したら良いではないかと思われるけれど、現実にケース2でやれるものでしょうか。
上(資格丁)からの考察と下(資格甲)からの考察をしてみましょう。
1.上(資格丁)からの考察
資格丁の上は役員です。この会社の役員退職金が、例えば4年の在職で6百万円程度だとしましょう。すると、1年あたりの支給額(=掛金年額)は150万円になります。
一方、親会社から56歳でこの会社に転籍して、4年間を資格丁にて勤務し退職した者は、ケース2の表によれば、1年あたりの支給額(=掛金年額)が78万円になります。
役員の掛金年額は、最上位の従業員の倍であることに驚くかもしれませんが、役員退職者は失業保険を受けられない(慣行です)のに対して、従業員退職者は失業保険が下ります。役員の手にする退職金から、失業保険金に相当すると思われる3百万円を除くと、残りは3百万円。これですと、1年あたりの単価は75万円。従業員の最高資格の退職者の1年あたりの単価並みになってしまいます。
役員退職金が適正なレベルであるとすれば、ケース2における資格丁の掛金年額は高すぎると考えられます。
また、また親会社から転籍した者の、転籍後の従業員としての退職金は、1年あたりの単価としては、15万円から50万円というのが一般企業の相場ではないかと考えられます。
転籍により56歳で資格丁で働く人も、新入社員から勤め上げて資格丁になった人も、一年あたりの掛金は同じであるべきと考えれば、資格丁の掛金年額78万円はいくら何でも高すぎの感があります。
例えば、中退共では、掛金月額が、5千円から3万円の範囲内で設定することになっています。年額に直せば、6万円から36万円です。掛金の最高額が36万円までしか認められていないことを考えると、やはり78万円はちょっと高いです。
ちなみに、401k(確定拠出年金)における掛金年額の上限は 432,000円です。
この金額を見れば、やはり掛金年額78万円はありえない値です。
(なお、確定拠出年金の掛金年額の上限は、更に引き上げるように見直しがされています)
2.下(資格甲)からの考察
新卒の新入社員が5年とか10年とか短い期間働いて会社を辞めるとき、一体いくらぐらい貰えるのでしょうか。中小企業では、1年あたり5万円から15万円程度の退職金が出るのが世間相場でしょう。
するとケース2の、最低掛金:年24万円は明らかに高すぎます。ケース2では4年(うち1年は見習い期間)働いて結婚退職する女性に72万円の給付です。殆どの人は、この支給は立派すぎると思うのではないでしょうか。
以上の検討からわかるとおり、要するにケース2では、掛金レベルが、世間一般の会社から見れば全く常識的ではありません。ケース1が掛金レベルとして妥当で、短期の勤続の場合の退職金に合致します。
ケース2はあり得ない掛金で、となると、金利1%を飲めば、2千万円の退職金の支給は絶対に不可能です。
ケース1での中途退職の場合の退職金を試算します。22歳新卒入社の者を対象にします。
(1) 38歳で家業を継ぎたいと申し出た場合
(資格 甲)12万円、9年→108万円
(資格 乙)24万円、5年→120万円……合計 228万円
(2) 48歳で退職を申し出た場合
(資格 甲)12万円、9年→108万円
(資格 乙)24万円、5年→120万円
(資格 丙)30万円、10年→300万円……合計 528万円
これなら、おおかたの会社は充分と考えることでしょう。
しかし、ケース1ですと、60歳定年退職では支給額が金輪際2千万円に達しません。どうしたらよいでしょうか。
社外拠出の年金積立の他に、(長期の勤続者のために)『一時金支給』の退職金を追加するしか方法がありません。
こちらのほうは、社外拠出の年金積立と違って決め方に自由が利き、会社に貢献があった人にたくさん退職金を積むことができます。
一時金支給の退職金は、満50歳に到達した時に受給の権利が発生するというような決め方が可能ですし、その計算根拠を、資格や職位に基づくポイント制とすることにより、管理職まで到達した人に、より給付を厚くすることが可能です。
資格や職位に基づくポイント制による一時金支給の退職金は、例えば満55歳にてポイント加算を停止する運用とするのがいいと思います。
私の勤務先では退職金を次の三つの構成としました。
1.社外拠出年金(中退共)〜入社の翌年から退職月まで積立……自己都合退職割引なし
2.資格に基づくポイント制による一時金
(1) ポイントの加算は入社日から満55歳までの期間で行う。
(2) ポイントは、最低資格で12点、最高資格で68点、5.7倍の格差をもうける。
(3) ポイント制による一時金の支払は、満50歳以上の退職者に適用する。
(50歳以下を対象にしないのは、自己都合退職減額に相当すると考えてください)
3.上記一時金を割増計算したもの……功労付加金として加算の扱い
(これは最終到達職位と貢献度によって大きく差をつける)
※1 満50歳になる前に退職した人は、1の支給だけとする。
※2 満50歳を超えての退職は、2と3とを加算することによって定年退職と同レベルの扱いとする。
※3 上級職位の者については、旧制度(適格企業年金制度)の給付額をほぼ守った。
※4 それ以外の職位で退職する者については、定年退職時の給付額を確定拠出年金の時より大幅にダウンさせた。
※4について
部長や課長にならぬまま定年を迎えた社員は、やはり会社にとって価値が低いです。60歳まで我慢して雇用してやって、年収(同レベルの仕事をしている若手社員より大層大きな金額)を与えてきたことで充分な処遇なのであって、退職金を、部長や課長の層とさほど違わない金額にすることはできません。
要するに、401kの確定拠出年金は利回り2.5%程度の設計を前提とするなら、これで退職金をすべてカバーするのは、実務的にはかなり無理があります。一時金支給の退職金上乗せによって、管理職等功労者に報いる必要があります。
蛇足:
生保とか損保の年金商品を扱っている人たちは、「中退共の運用利回りは1%強程度の低水準だから、とっても馬鹿馬鹿しいです。我が社の年金商品は運用利回りを2.5%にしているので、こちらのほうが断然にお得です」と言います。
しかし、このご時世ほんとうに2.5%が可能なんでしょうか。私はそんな利回りは期待薄だと思います。どうも現在の商品は、5.5%をあきらめて、2〜3.5%あたりを狙うものが多いようですが、これは眉唾です。国債や、銀行の5年物の定期の利率を考えてください。
もし1%ぐらいにしかならなければ、結局会社が不足額を出すことになります。先に出せるなら良いけれど、後になって出させられるのはとってもつらいです。
現実的な利率で年金を設計し、給付総額で足りない分は一時金加算とするのが正解だと思います。一時金のほうは、本当に会社に支払能力の点で厳しくなったのなら、カットするだけのことです。
ということであれば、これからは、給与所得人は、給与所得を喪失する年齢に至った時に、貯蓄が2千万円ぐらいはあることが望ましいという結論になります。
ソープに嵌めに行くから、そんな貯蓄なんて、できっこねえ、と思うのでしたら、自民党に投票して『消費税率15%』を実現させるより他はありません。
(千戸拾倍 著)
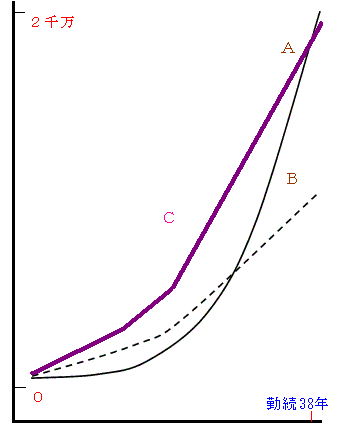 縦軸が退職年金の一時金評価額で、横軸が勤続年数です。取りあえず、縦軸は2千万円を上限値とし、横軸は大卒22歳入社・60歳定年・38年勤続を上限とします。
縦軸が退職年金の一時金評価額で、横軸が勤続年数です。取りあえず、縦軸は2千万円を上限値とし、横軸は大卒22歳入社・60歳定年・38年勤続を上限とします。