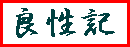
18歳未満の方は入場をご遠慮下さい。
梓 4
ベッドの絡みを始めた。
梓がいつものようにベッドの端に尻を置き、仰向けになった。陰阜がこんもり浮き出て、いびつな形をしたラビアが覗いた。
私がベッド際の床に膝立ちすると、梓の股ぐらが私のへその高さだった。
(さあ、また、よがってもらおうか)
私は上体を屈め、梓の股間を覗き込んだ。梓とは抱き合って前奏的にキスしたり、中指一本でペッティングしたりはせずに、いつもいきなりクンニリングスから始めた。
キスしても梓は唇をあまり開かず、舌先を探り合うような応答をしないから、面白くない。性器への愛撫にしても、指より舌でされるほうがはるかに気持ちが良い、とはっきり言うから、さっさとクリトリスを舐めて梓を昂まらせ、私もよがり汁の匂いで亢奮することにしていた。
その体勢での前戯を予期していた梓は、ベッドの端に斜交いに寝そべったので、右足はベッドの上で、左足は外につき出し宙ぶらりんにして大股開きしている。臑がすらーっと伸びた脚は殆ど筋肉が発達していないから、腿や脹ら脛の肉までぶらぶらした感じだ。
私はその足を右肩にかけ、それまでの感傷と逡巡の心の乱れを追いやった。
いつものように乳房は皺を無数に浮かべてつぶれ、二つの干しぶどうだけが目立つ。目を瞑った顔とシーツに広がる豊かな髪が見馴れた魅惑だ。
浅黒い腿を両肘で押し拡げると、皮膚が伸びても、陰核茎部の棟と大土手と小陰唇は着色が立派だ。長い包皮がクリトリスに深く被っているのも面白い。強引に剥き上げて、中に恥垢がたまっているのを見たことがない。これだけややこしい起伏があるのに、梓は陰部の洗浄がいつも入念であることがよくわかる。
梓の卑猥な肉の造形にはもう長い間馴れ親しんでいるけれど、私は飽きもせずにいつものように虚心に愛撫した。
クリトリスの長い包皮を目一杯剥き上げて、紅い宝石を唇で揉み、舌の真ん中に包むようにこすり立て、舌先ですくい上げ、充血の感触を楽しんだ。
しばらくすると、梓の最初は開いていた指が、次第に何かものを掴むように指先の関節から曲げられて、坂を上り始めたことがわかる。
私の右肩にかけた梓の左足は、横に倒れるように開脚を深め、土踏まずを私の首筋にあてがって、時々震わせている。淫らなポーズだ。
股間に愛液が仄かに香りだし、梓はいつもよりもかなり早めに、「指、入れて!」と叫んだ。
私は唇で充血のボタンを捉えたまま、掌を上にして肉壷に二本の指を入れてゆるやかに出し入れし、膣の中ほど上部にある、顕著に襞を刻んだ箇所の裂け目の感触を指先で探った。
そのまま二本の指を半円に回転させると、梓の肉壺の断面が丁度凹の形をしていて、上部が微妙な起伏に富んだまま広く長く盛り上がっているのがよくわかる。
私はクンニリングスをしていた唇を離し、梓に声をかけた。
「本当に、お前のこの部分が、肉が盛り上がって、いいんだよなぁ。ちんちん入れると、こすれ感がいいんだよなぁ。……ずーっと、ちんちんを入れさせて貰ったこと、ないけど」
「みんな、形が違うのねえ。……ああっ……どういうふうに違うのか、知りたいわ。……ああっ、そう」
「おまんφは皆違うんだぜ。ほんと、色も形も匂いも違う。ローザちゃんなんかとっても狭いよ。ちんちんを嵌めるとギンギンにきついと思う。由美のクリトリスは見事に大きくてとっても魅力的だし。……うん、おまんφ汁がいっぱい出ている!」
夏美の場合は、おまんφが濡れて黒々とした陰毛がベタッと張り付いているのが良い、と解説しかけて、夏美のことは隠しておこうと喉の奥にのみ込んだ。
唇のまわりから鼻腔へ、生臭いような懐かしいようなラブジュースの香りが漂った。眼前の陰裂は卑猥なまでに赤黒く花開き、中は柿色に光って、膣道が吸い込まんばかりに指二本の進入を受け入れている。
たまらなくなって、また股ぐらに唇を寄せた。
私は陰毛をかき分けてクリトリスに一心不乱に吸いつきながら、窮屈な構えでせっせと指を動かし、上目遣いで梓の下腹や胸や顎の揺れ方と波打つ様を観察した。
床に腰を下ろした私の右手は、Gスポットを刺激すべく膣の角度に沿って斜め上方へ繰り出す動きだ。男の手としてはかなり小さいので、指が奥まで届かないのがもどかしい。
その手の甲に中指の背から愛液が伝わった。それが手の甲をびしょ濡れにして、手首の辺りまで流れてから雫になってぽたぽたと滴り落ちるのを、私はあぐら座りの毛臑で受けて、冷やっこい感触を愉しんだ。
(今日の梓は、おまんφがむちゃくちゃジューシーだぜ!)
二本の指を膣壁の上部に強く押し当て少し回転させるように動かし、舌先でリズミカルにクリトリスを弄うと、梓の喘ぎ声が高くなった。
私は梓の昂揚が指のピストン運動によるものなのかクンニリングスによるものなのか測りかねていた。
喘ぎ声のピッチが早くなったのでどうやら快感が頂点に近づいたようだと思い、私は肉孔に嵌めていた指を抜いた。両手で陰唇の上部を押し上げ、割れ目の濡れ具合と充血の様を観察すると、梓は愛撫が途絶えたからエクスタシーへの欲求で腰をよじらせた。
私は仕上がりが近づいたのを愉しむように舌を差し出し、クンニリングスの動きを早めた。有機物質が過飽和になった磯のような濃厚な匂いが漂っている。
間もなく梓は悲鳴を上げ、身をよじって深々とアクメに到達した。割れ目を隠すように両膝を引きつけると、濡れた会陰とアナルがいやらしい。
私は眼鏡をかけた。梓の陶酔の横顔を眺め、梓のよがり汁が腕を伝ってたっぷり滴り落ちて毛臑を濡らして光らせているのを認めた。
ベッドインの初めは眼鏡を外してクンニリングスをし、梓からフィンガープレイを受ける時には、眼鏡をかけて、梓が妖艶な顔でペニスを卑猥にこすりたてるのを観察することにしていた。
梓はいつもと違ってそのままぐったりと寝そべっていた。腰の横に見えるシーツの染みがやけに大きい。
(今日の梓の絶頂はかなり深かったようだ。……こいつのおまんφを舐めるのを本当に今日が最後にするのか? 俺以外の男で、ここまで濡らすことはないだろうに!)
私は床から立ち上がり、唇の疲労感を充実感に昇華させながら、梓の傍らに躯を横たえた。天井に向く眼は焦点も合わせず、何も考えないで、梓がローションを仕込むために起き上がるのを待った。
しばらくして、梓は無言のままベッドから立ち上がり、ローション液を掌に溜めてベッドに戻ってきた。
梓が私の開いた脚の間に座り、生温かいローションをペニスに塗りつけた。いつもの、快感は飛び抜けているが、それだけに何となく虚しさが私の心の中に残る、猛烈で巧妙な手淫が始まった。
私は梓が愛撫しやすいように脚をたたんで膝を引いた。
金的もアナルも愛撫しやすい淫らな格好になったところで、梓はカリ首を握ってこすりはじめた。やがて、ペニスを握ったまま私の内腿から菊座にかけて舌をチロチロと這わす動きを加えた。四つん這いのまま、頬がシーツにつかんばかりに顔を下げる窮屈な体勢で、優しくリズミカルに舌先が往復している。
私はおやっ!と思った。何か情愛を感じさせる動作だった。
梓はマットでは指技と舌使いの同時発揮の愛技を丹念にしていても、ベッドプレイはいつもいきなりペニスにローションを塗りつけて手でこねまわした。口唇愛撫を併用するのは記憶になかった。
私は梓がペニスを握ってしごくのを楽しみながら、梓が最前にクンニリングスで気をやった後、数十秒間躯を折って横向きに寝そべっていたポーズを振り返った。
今まで、梓は気をやった後、ベッドの上で寝そべったままにしているようなことは殆どなかった。自分が到達すれば直ちに跳ね起きて、如意棒を攻撃する準備にかかった。
(今日はいつもと少し違う。こいつ、しばらくぼーっと寝ていたぞ。お汁の量も随分と多かったし。しかし、こんな長い付き合いなのに、自分がイッた後、知らん顔で私に背を向けて横寝するのではなく、私の躯に手を伸ばして肌を撫でるとか、甘い言葉も囁くか、胸に顔を埋めるか何か、ぐっとくるようなことをする可愛らしい性格ならば、常連客を一人失うこともないのに)
(でも、そんなことはわかっていて梓と長年つきあってきた。強がって生きている、こういう性格の女なんだ。所詮風俗の遊びなんだからこれも一興なのではないか)
梓は私の腰の後ろから両手でペニスを揉みながら、犬が水を飲むように頭を下げて、内腿や尻の狭間に舌を這わせた。意外にも舌先でアナルを突っつくようなこともした。
しばらくすると、カリ首をさするのは左手だけを使い、シーツについた右の肘をずらしながら、四つん這いのまま私の両脚の間から腰の右側にいざり出た。
私が上げていた両足を下ろすと、梓は鼠蹊部を舌で掃いてから玉袋にぬらーっと舌を這わせた。何度か掻き上げるように撫でてから、睾丸を唇で圧迫する動作を繰り返した。同時に左手は、人差し指でペニスの裏筋のあたりを支え、親指でカリ首の背をこすっている。
得意のマルチ愛撫を念入りにしながら下半身を私の右脇にじわじわと寄せた。
梓の豊かな尻が正面から見えるようになった。四つん這いになって突き出した尻は体積に迫力がある。その真ん中の、菊座から陰裂までの着色の濃い部分は下から眺めると何とも卑猥に見えた。
梓は69では自分が快感に集中することができない、と嫌っていたので、私はこの角度から梓の陰部を眺めたことがあまりなかった。
男の股間を同じ角度から見た場合、アナル、女に比べれば長い会陰、ふくらんだ睾丸、そのあたりの肌に対して直角に生えている陰毛、その一連の構図がユーモラスに思えるけれども、女の、アナル、短い会陰、奇妙で不自然な形をした割れ目、アナルから陰唇下部の肌に這うように生えている恥毛、その眺めは猥雑としか言いようがない。
雌の生殖孔と排出孔が雄にとってはこれほどまでに魅力のある眺めなのかとつくづく感心する。
縦に走る深い溝を囲む壮大な肉の丸みと、アナルから少し離れたところで突起しているのが目立つ毛穴の集団が円形状に散っているのをしばらく見とれていた。
(この深い溝は、人類誕生と揺籃の地、アフリカ大地溝地帯のように大きいぜ。すると、アナルはキリマンジャロか?……)
そんな対比をして変色地帯を凝視した。
梓は舌で金的を丹念に掃き続けた。同時にペニスをねっとりと手揉みしている。
この日ばかりは完全怒張に到らないのでは、と危惧していたペニスが、ローションにまみれて光沢を放ち力強く存在を誇っていた。梓の十本の指を駆使した強烈なこすりに、粘液が泡立ち、カリ首は力みかえって摩擦音を立てている。
(今日の愛撫はやけに長いぜ。時々カリ首をこするのを止めて、すぐに射精しないように工夫している。それに丁寧で熱烈大サービスだぞ。それにしても、金玉のように臭いのこもりやすいところをそんなに長く舐められるなら、ディープキスもしっかりしてくれればいいのに)
ペニスに塗ったローションはもう乾いても良い頃だけれど、先走り汁が充分に潤滑を助けて、激しい摩擦でも痛みは感じない。
梓も、指が滑らかにすべらなくなると時々カリ首に唾液を垂らして補った。気合いの入った手掻きにペニスは張りを満杯にしたままだ。
梓はカリ首を親指と人差し指の間でしごき、人差し指と中指の間からヌルーッと出したり、また中指と薬指の間をくぐらせたりして弄び、硬度の感触を愉しんでいる。笠の張りだし具合を確かめているようだ。
いつものことだが、梓の指使いは穂先にひねりの力が加わって気持ち良い。超ベテランのオナニスト級のマジックハンドだ。
カリ首を包む梓の手から、また豪快な尻に目を移すと、ゆさゆさとその尻が揺すられ、股間のほうから梓の声が聞こえた。
「指、入れてぇ!」
(こんなことを言う美人ソープ嬢は、そうはいないぜ。お前、本当に梓に会うのをやめるんか?……)
私は手を伸ばし、中指を挿入して中で内側に曲げた。肉壁を探り、粘液を絡めて遊ぶその指を支えにして掌を押し当てて、女芯の辺りを圧迫して揉んだ。
掌の手首辺りが陰核茎部の盛り上がりに接する感触は、同時に恥毛が当たるじょりじょりした感覚でぼけてしまう。中指ができるだけ奥まで入るように、人差し指と薬指を反らすように伸ばし、その二本の指で梓の尻たぶを押し拡げた。
両指の間に覗く褐色のアナルが孤高の噴火口のようだ。
味わいなれた激しいこすりの、巧妙な手技が続いた。梓は攻めのツボが完全にわかっている。私は朦朧とした状態になって喉元から低いうなり声が出はじめた。
梓は、私を落とそうと思うと、いつもペニスを両手でくるんで揉む。接触面積を大きく、振幅を短く、圧迫は強く、右の掌はなるべくカリ首にとどまり、左手は大きくスライドして、鈴口から睾丸まで刺激する。笠にネットリ指を引っかけ、とても良い圧迫だ。
私は全神経がペニスに集中し、全身がペニスの組織になったような気がする。否応なしに、脳から不随意の伝令が飛ぶ。
完璧の噴出の、私の絶叫が廊下にまで響きそうなフィニッシュで、ベッドプレイのすべてが終わった。
梓がペニスを根元からしごいてティッシュで後始末をすると、私は、その日久し振りに梓に入った訳を、言ってしまって良いのか迷いながら、ぼそぼそとした口調で説明した。
「由美に最近全然入れないんだよ。実は昨日、由美を予約しておいたんだけど、今日あの子は休んじゃっただろう。だから、梓のところに来たんだぜ」
珍しく梓は、ウイットに富んだ言葉を返すこともなく、ニヤッと笑うこともなく、黙って私の顔を見た。そして、気のせいか引き吊ったような笑みを浮かべて言った。
「由美ちゃん、今、自動車の免許を取るのに一生懸命だからぁ。先月は十三日しか店に出ていないのよ」
(梓を可愛い女だと思って惚れ抜いて、女房にしたい、という男が現れるのだろうか。男と遊ぶことはできても、男に尽くすことができると相手に思わせることがこの女はできるのだろうか?)
梓はシャワーを使いながら、正体不明の女のことを盛んに知りたがった。
「誰なのぉ、その女?」
「そのうちにわかるからさぁ。同じ店なんだし」
「だったら、今、教えてよ」
私は、生返事で服を着ながら、先ほどまでの梓の言葉を思い出していた。
「そうよ。でも、あの子に訊いたら、あの子も私をイカしたと言うかもしれないわ」
「うふっ、そうなのー。内緒よ」
「一体その子、誰なのよ。言いなさい。二十本取る子なの?」
「××さん、大分前に由美ちゃんに、もう私のところに来るのをよそうかと相談したんでしょ。……で、今日来ているじゃない」
「でも、最近は演技が上手な子がいるのよ。古い子でも、××さんがよく来る人だって知っていれば……」
「昨日の男は良かったわよ。延々とセックスしてた。好みの男だったからぁ。私だって、プライベートにセックスをする男がいるのよ」
「みんな、形が違うのねえ。……ああっ……どういうふうに違うのか、知りたいわ。……ああっ、そう」
「指、入れてぇ!」
私を送り出す梓の顔がその日は一段と妖艶に映った。
六年も前から梓の常連となって、毎度わくわくして予約を入れ、コストをかけて築いてきた親和の世界が消え去るのが何とも残念な想いがした。
私が名前を隠していた夏美についてはやはりすぐに梓にばれた。
これが梓に会う最後だと心に決め、別れの入浴をした後しばらくして、私は夏美に予約を入れた。
夏美と一緒に店の四階でエレベーターを降りたところで、若い男前の客を連れた梓とばったり出会った。
「あらーっ!」
嬌声を上げた梓はこれから客を伴って部屋に入るところなのに、客を放ったらかして、私と夏美の二人の組み合わせを初めて知ったかの顔で冷やかした。
薄暗い廊下で、梓の瞳が悪戯っぽく光っていた。
夏美との情熱遊戯が終わって、身繕いをしようかというところへ、梓がドアをノックして入ってきた。
梓も私が夏美に入ったのと同じ時刻に客を案内し、梓のほうが早く仕事を終えていた。さすがに「早上がりの梓」と呼ばれるだけあって、既に客を送り出し、部屋の後片付けも済んでいた。
梓が部屋に来たので夏美が驚いていた。
私は以前由美と逢っていた時もローザと逢っていた時も、私が来ていることを梓が知ると、部屋に入ってきて歓談したことがあるので、ひょっとしたらまた現れるかもしれないと思っていた。
私がローザに逢っている最中に梓が覗きにきたときは、堂々と乗り込み、ローザには声もかけず私に話しかけた。ローザは驚いて正座して、最初は緊張していたけれど、梓と私のやりとりがふざけた調子だからにこにこして見るようになった。
ローザの、五つ年上の先輩の前で恐縮したような姿勢がユーモラスだった。
ローザは梓が部屋を去った後、しみじみとした口調で言った。
「××さんと梓さんって、お互いにずけずけときつい冗談を言い合ったりして、本当に親しいんだなぁと、私、思ったわ」
そんなことを思い出した。
しかし、実際に梓が夏美と私のいるところに入ってくると苦笑せざるを得なかった。
「××さん、新しく好い子を見つけたと言っても、名前は教えてくれないんだものー。夏美さんだったのね。私、びっくりしたわ」
梓はすぐにスリッパを脱がずに入り口に立ったまま、眼を見開いて私の顔を舐めるように見つめた。
ニヤリと笑って、ベッドに腰掛けていた私の横に座ると、梓は大声で喋った。
「××ちゃんね、最近入りはじめた女の子に、でれでれにご執心みたいだったの。その女の名を××ちゃんは決して私には明かさないの。由美ちゃんやローザちゃんのときにはちゃんと教えてくれたから、ちょっと変だわと思っていたのよ。今までにそんなことがなかったから、私、それがとっても不思議で、しかも、夏美さんだったとわかってほんとうに驚いたわ。なるほどーと思ったわよ」
話は夏美に聞かせている言い方でも、視線を殆ど私に向けて盛んにからかった。
夏美が会った回数はまだ少ないというように演技をしたので、私も話を合わせた。
梓は真に受けた口ぶりで、なおも私をあれやこれやと冷やかしていた。
私は素裸だから、夏美に対して使用したばかりの萎びきったものが包茎状態で蛸壺のようになって、精液の残りをにじませているのを、ユニフォームを着た梓の眼前に晒していた。
(むちゃくちゃ格好悪いなぁ、でも、こいつ以外の女の中に純生で発射したばかりの俺のちんちんを、縮こまったこれを、こいつに見せつけるのも面白かろう)
そう思っていたら夏美が、「この人、本当にマットで注文がうるさいのよ。ああしろ、こうしろって」とこぼしながら私の腰にバスタオルを投げた。
それまで私は、梓がエレベーターのところで私と夏美に出会って初めて知ったと思っていた。が、私と夏美の示し合わせたような嘘の話を聞き終えた後、梓は、私が最近誰に入っているのかパソコンの予約表を見てわかった、とニソッと打ち明けた。
客のプライバシーだから、そんなものは女に覗かれないようにしているけれども、梓はたまたまそれを見たのだろう。それで、とぼけた顔で私と喋りながら、二人が嘘を言うのを面白がって聞いていた。
梓には、夫が本妻公認の妾と団欒しているところに乗り込んだ本妻の雰囲気があった。
本妻は美貌のところに、仕事を終えて化粧を仕上げている。妾のほうは美貌ではない上に、仕事の途中で化粧が乱れきっている。落差が激しい。
「××さんはねえ、何を言っても絶対に怒らないわよ。本当にいい人よ」
梓は夏美にそう話しかけて艶麗な流し目を私に送り、ベッドに指先を向けた。
「このシーツの染みは誰の?」
そう尋ねてから、なおもあれやこれや喋り続けていた。
(円形の大きな染みなんぞ、俺が作る筈がないのに、わざわざこんなことを言って、こいつー。エレベーターの前でばったり会ったのも、梓が、自分の次は夏美が同じ階に俺を案内すると知って待ち伏せしていたに違いないぞ。梓は、もう俺が会う気はないことがわかっているのだろうか?……だけど、こいつは本当に別嬪だ。どうしようもなく美しい。実に綺麗だぜ!)
通うのを止めてしまうのがとても惜しいような気がしてならないが、私は女御と更衣が火花を散らしているシーンをふと連想して梓の妖艶な瞳を見つめた。
その日梓が現れる前、夏美と私は結構梓のことを話題にしていた。
夏美は私の前で初めて「梓」と呼び捨てし、珍しく梓について非難めいたことを語った。夏美はどうやら梓よりも年上らしい。
由美が梓にいつもくっついているもんだから梓に感化されて、指名があまり稼げない女を侮り、からかう、思いやりのない傲慢な態度を取ったり、基本的な礼儀をわきまえたものの言い方ができない、鼻持ちならない女になりかけているという趣旨の話をした。
自分が梓の古い常連だから、直接梓をそしるのは避け、由美を引き合いに出して間接的に咎めているのだなと私は察した。夏美の指摘に同感しながら、ああ、女の世界だなあ、と思って聞いていた。
それからしばらくして夏美に逢った。
梓がシーツの染みを気にしていたのを思い出して、尋ねた。
「ひょっとしてあいつは、君が僕にサックを使っていないのでは、と想像しているのではないのかな?」
「彼女、貴方を送ってから、えらく丁寧に部屋の後片付けを手伝ってくれたから探っていたかもしれないわ」
夏美が答えた。
使用済みのサックをどう処置するかは、皆、同じ方法だから、使用した痕跡がないのを梓は確かめたのかもしれなかった。
あの日、服を着終わって佇んでいた夏美と、まだ裸のままベッドに腰掛けていた私を相手にして、梓が独りべらべらと喋っていたのは異様な雰囲気だった。
私が梓に入った時、今日が最後だよという態度をはっきりと示したくても、未練な気持ちがわき起こり、意志表示ができなかった。でも、夏美に逢っているときに梓が乗り込んできて、夏美の前で腹を立てたくなるような皮肉を言ったので、やっぱり梓は察知したようだと感じた。
そんなふうに思いながら、私は夏美に、もう梓には入らないよ、と宣言した。すると、夏美はそのことについては何も触れず、想い出話をした。
「梓さんはね、ちょっと変わった性格よ。普通の女の子のような喜怒哀楽の心がないの。皆でテレビドラマのとっても感動的で素晴らしいのや悲しいのを見ていて、全員がぽろぽろ涙を流していても、梓ちゃんは涙なんか流さないの。それどころか、『皆、こんな物語なんかで、どうしてそんな涙なんか出すの?』と、本当に不思議そうな顔をするの。
『ちょっとあんたー、これを見て本当に目頭が熱くならないの。あんた、少しも感動しないの?』と訊いても、『全然、少しも。私、子供の時から泣いたことなんか一度もないわ。だけどみんな何故これを見て涙を出すの? こんな作り話で、どうしてぇ?』と言うもんだから、皆、『へーぇ!』と、顔を見合わせて驚いていたの」
梓に生んだ子供のことを気にかける様子が少しもなかったのとその話は釣り合っていた。
私は梓のことを冷ややかに語る夏美の顔を見て、どうしてこの女は梓と比べて器量が断然見劣りするのだろう、と思い、また梓を懐かしむような気持ちになった。
平成六年一月夏美に逢った日の翌日にとんでもない事件が起きた。恵里亜が警察に検挙された。
その頃金津園で店の手入れはしばしばあった。でも、私の出入りしてない店ばかりで別の世界のことだと思っていたので驚天動地の出来事だった。
梓も由美もローザも夏美も、皆行方不明になってしまった。私は、女と親しくなっても電話番号を聞き出そうとはしなかったから、探す手がかりが全くない。絶望のどん底に突き落とされ、憂鬱な日々を送った。
梓に会う気はなかった筈だけれど、思いもよらぬ店の手入れで他律的にも会うことができなくなると、迎賓閣からいなくなった時の、涙を流した悲嘆ぶりをしみじみ思い出した。
もし梓が金津園のどこかの店に出ているとわかったなら、会いに行くべきか、会いに行くのだろうか、自分の気持ちがわからなかった。
(惚れているからこそ、梓には厳しい見方を俺はしているのだ。あんなに俺をわくわくさせ、愉しませてくれた女なのに)
私は梓がフェラチオを殆どしないことが不満だった。
そのことを由美に愚痴ると、由美が言った。
「梓さんは××さんがちん汁をたくさん出すのが苦手だったのよ。梓さんが『××さんのおちんちんの先走り汁は、臭いや味はあまりしないけど、信じられないぐらいにいっぱい出てくるんだから、参るわ。口でおちんちんをくわえたら、途端にもうダバダバと生温かい汁が流れてきて、気持ち悪いったらありゃしない。あれさえなければ、私、××さんにちゃんと尺八もしてあげるのだけどぉ、どうして××さんはあんなにちん汁が出るのかしらぁ! あれがいけないのよぉ。あれさえなければ。もう、会ってパンツを脱いだら、おちんちんの先から透明なねばねばをだらーっと垂らしているんだから、そんな人、他に見たことがないわよねえ。あのべとべとは、ほんとにすごいわよぉ』と、もうオーバーな顔をして、控え室で盛んに話題にしていたの」
迎賓閣の時、梓は肉棒の中にたまった先走り汁を吸い込むと、吐瀉物を口内に含んだような顔をしたから、不愉快のような愉快のような妙な気持ちになった。
「お前だってべとべとにするのを俺は何の苦もなく思っているのに」
「だって、貴方はそれが好きなんだからぁ。私は、いやなものはしょうがないじゃないの。少々の量ならいいんだけれどぉ」
そんな会話を何度かした。
梓はフェラチオをする前にペニスをしごいて、わざわざティッシュで粘液を吸い取るようなこともした。そうしても全然効果がなくて、また新たにドーッと滲み出てくるので盛んにあきれていた。
私はそんな梓の表情と仕草を振り返り、梓のことを懐かしんだ。
ソープ嬢は客のセーターや下着をたたんで籠にしまう。常連客であるとその籠の中に自分の下着も男の下着に並べて置く。
脱いだばかりのパンティのたたんであるのは本当に可愛らしいといつも思っていた。それを取り上げて股ぐらのところを眺めてもシミや変色を見つけたことは一度もない。
仕事着だから当然なのだが、そういう検分をした時の、梓、由美、ローザ、夏美の反応の違いがそれぞれの性格を示して面白かった。
夏美は「可愛いのでしょ。……××さん、穿いてみてよ」と言った。
ローザは「穿いてみるう?……わぁ、可愛い。似合う! おもしろいー。たまたまさんが、××さん、左右に飛び出ているわー。いやだー、あはっはっ」と騒いだ。
由美は、いたずら坊主という眼で微笑んで見ていた。
梓は「そういうもんは見るもんじゃないの」と言って取り上げようとしたので、私がパンティを頭に被ると「汚れるー! でも、似合うわ、××ちゃん」のサディスティックな眼差しだった。
梓のパンティを頭に被ったのはまだ梓が迎賓閣にいた頃のことだ。
更に私は以前に梓が言ったことを思い出した。
「私、店の子に教えてやったのよ。『××さんのセックスは他の人と違うのよ。部屋の中の声をドアーの外で聞いていたとすると、最初に女の子の大きなよがり声が聞こえるの。そして、女の子が気持ち良さそうにイク声がした後、しばらくして××さんがイク声が聞こえる筈よ。その唸り声が大きいの。それでもって二人の声は同時じゃないの。××さんがイクときの顔も本当に面白いわよ。まさしくイクーぅという感じなのぉ』って。……本当にそうだよねえー、××さん。その通りだもんねえー、××さん」
(あいつ、私が、由美か誰かに入ったときに、面白がって立ち聞きしていたに違いないぞ)
そんなことを想像し、梓の悪戯ぽい妖艶な表情を頭に浮かべて溜息をついた。
私は金津園のいくつかの店を短期間で探し回ったが、常連で通った女の誰も行方がつかめなかった。すっかり失望し悶々としていた。
ところが、検挙の二ヶ月後になって、ソープ情報誌でローザがヴィーナスに出ているとわかった。
私は勇躍してローザに逢った。
ローザは由美と夏美の消息を知っていたが、梓については知らなかった。ただ、私は他の店で、恵里亜の有力な女は皆吉原へ行った、と噂を聞いていた。
ローザのもとを去る帰り道に、私は金津園の外れにある産婦人科医院の前を通った。そこは金津園の女がよく通うF医院で、身なりがソープ嬢らしき若い美人が扉を開けて入ろうとする姿の、胸と腰の線を眼で追いかけていたら、中から見馴れた顔が出てきたのでびっくりした。
梓だった。
素面でも、やはり眸子から男の眼を射抜くような妖しい放射線を放っていた。洗いざらしの長袖の、白地のシャツは、子犬の柄がちりばめられている。木綿地のようだ。スラックスも木綿系で、折り目は作っていない。普段着の寛いだ格好をしていた。
殆ど化粧していない顔を白昼日光の元で見ても、やはり梓はとても良い女だ。
スラックス姿を見るのは、梓が仲間と東京ディズニーランドへ出かけた時以来だった。
いつも、素っ裸か店のユニフォーム姿しか見ていないから、私服姿がもの珍しくてならない。それも、名古屋駅で見たような上等の外出着ではなくて、洗い晒しの普段着を着て、とても新鮮さが眼に映る。
私は最前ローザの中に放出したばかりでも、下半身にエネルギーが満ちるのを感じた。
「あらっ、どうしたんだ。今、どこにいるの?」
「××さん、今日、誰に入って来たの?」
私が歩いてきた方角を確かめて答も返さずに逆に質問してきたから、梓は私に言いにくいことをしているのかと思った。
「ローザちゃんだよ。今日発売のこのM誌を見て、ローザが出ているとわかってすっ飛んで来た」
「そう、ローザちゃんに入ってきたの。××さん、良かったわねえ。あらっ、M誌、持っているの。それ、私に見せて。ねえ、駅まで送ろうか。乗っていく?」
「じゃあ、頼むよ」
黒い車はBMWだった。梓は、発車せずに、雑誌を膝の上に置いて、忙しげに雑誌を捲った。
私は雑誌とズボンと下着を透視して、恥毛の生え方と太腿の付け根が股ぐらを隠している眺めを辿っていた。
「恵里亜が捕まって、本当にがっくりしたぜ。あの店が手入れされるとは、全く考えもしなかった」
「私もびっくりしたわ、あの店が挙げられるなんて。私、結構長くやっているほうだけど、あんなの初めてよ。××さんもあの時恵里亜に来てなくて良かったわね。私は休みの日だったけれど、××さんが来ていたんじゃないかと心配したのよ」
「僕は、昼間には来ないから、手入れに直接出くわすことはないだろう」
「そうだわねえ。ここに来るのは夜ばかりだもんねえ」
「あれからいろんな店を六軒も探したんだよ。六つの店を覗いたんだぜ。どの店も、恵里亜の子は一人も働いていなかった。あんた達を捜すのに俺も大変だったんだ。無駄な金を使っちまったよ」
「そうなのぉ。ご苦労さんだったわねえ。でも、いろんな子に入って、楽しかったでしょ?」
「いやいや、初めての子はムードが出ないから嫌だ。馴染みの女の子がやっぱりいいよ。おとなしく雑誌が出るのを待っていれば良かった。それで、君は今どうしているんだよ?」
「私、吉原にいるのよ」
「何だって! ローザは君がまだ決まっていないようなことを言っていたぜ。へーぇ、やっぱり吉原だったんかぁ。思いきったものだ」
「××さん、私が吉原に行っていること、内緒にしていてよ。吉原に行っているのを教えたのは、夏美さんと由美ちゃんだけなのだからぁ。ローザちゃんは知らない筈だわ。金津園は今はどこの店も危ないから、私、しばらくは吉原にいることに決めたの。向こうに四日いて、こちらに三日戻るの」
「それで、今日は何故この医院なんだよ?」
「検診は今までのところが一番いいから、ここに来ているの」
「ふーん、婦人科なんだからそうだろうな。……吉原は、仲間と同じ店かい?」
「ううん、皆、別の店」
「何という名の店?」
「××という名よ。知っている?」
「ううん。総額幾らの店?」
「六万円よ」
「ええっ、六万! それでも君は、サックは使うんだろう?」
「私は絶対使うわよぉー」
「六万円の店ならば、即尺もノーサックも君が応じないとなると、店のほうは、気分が悪いだろうに」
「でも、私に歓んでくれるお客もいるからいいの」
「僕は車のことはさっぱりわからないけど、これ、高いんだろう?」
「三百万よ」
「へーぇ、たいしたもんだ。……すぽんと払ったんだろうねえ?」
「そうよ。××さん、由美ちゃんと夏美さん、今どこに出ているか知ってるぅ?」
「ローザちゃんから聞いたよ。皆行き先がわかって、安心だ」
「××さん、由美ちゃんと夏美さんのところに行ってあげてよね」
「勿論。だけど、君が吉原なんかに行くことはないじゃない。新幹線代だって馬鹿にならないし。大体、東京なんてところは人間の暮らすところじゃないよ。戻っちまえよ」
「でも、全然手取りが違うもん。今の店、一本つけば三万円以上入るのよ。金津園は本当に手取りが少ないの。吉原は倍は稼げるもん」
「人間、金だけじゃないよ。君はたっぷり支度金、貰ったんかい?」
「ううん、私はフリーで行ったから、そんなのは貰っていないの」
「それなら、いつでも足が抜けるな。そのほうが安心だ。早くここに戻ったほうがいいよ」
「警察に行くのはもう嫌。とにかく今の金津園は危ないから、しばらく様子を見ることにしたの。××さん、タバコ一本頂戴」
既に車は駅に着いていた。
梓の隣の助手席に座っての談笑は愉しいものだったが、縁を切ろうとした女だ、惚れなおしちゃあ駄目だ、と私は自分に言い聞かせながら喋っていた。
よく見れば、やはり三十が段々と近づいた顔だなと思い、梓のこれからの幸せを祈って車から降りた。
しばらくして私は由美に逢った。由美はルネッサンスに出ていた。
F医院の前でばったり梓に会ったことを由美に教えると、次の会話になった。
「××さん、本当に梓さんとの付き合い、長いのねえ」
「そうだよ」
「××さん、梓さんに会うのを止めるつもりだったの?」
「どうして知っているんだよ?」
「この前××さんが梓さんに入った後、彼女、私に『今度、××さんがあんたのところに来たときに、××さんが私に入るのを止めるつもりなのか、聞いてよ』と言ったの」
「梓とは長いつき合いだけど、あいつと会っても情感がないからもう止めだ。情緒がないぞなんて、梓に言った以上、恵里亜が挙げられなくても、僕はもう梓には入らないつもりだったんだよ。彼女に初めて迎賓閣で会った後所在不明の時期もあったけど、六年前からの付き合いだよ。長いよなぁ。迎賓閣にいたときは、僕は梓以外の女の子には殆ど入っていなかったもん。しかし、そんなことを君に言って、どういうつもりなのかなぁ?」
「私、どうしてっと聞いたのよ。そうしたら彼女、『××さんが来ないなら来ないで、もうバージニアスリムを置かないから』だって」
「ははっ、あいつらしいなぁ。でも、梓はいいところがあるねえ。この前は、駅まで車で送って貰ったんだよ。僕の持っていたM誌を取り上げて熱心に見ていたぜ。一体何を調べていたのかなぁ?」
「梓さん、吉原に行っていることは恵里亜にも仲間にも内緒なのよ。知っているのは私と夏美さんだけだと思うわ。ローザさんは知らない筈よ。彼女、今、六万円の店に出てるのよ。純生と即尺が売り物だけど、梓さんはそれはしないんだって。ピル抜きをしているところだと説明しているそうよ」
「へーぇ、超高級店なんだ。美人は得だねえ。あいつが、六万円の店なら純生のセックスも即尺もするというなら、俺は真剣に怒るぜ」
「本当にあの人、美人だから、私、羨ましいわ。素面でも相当なのに、ちょっと気を入れて真面目に化粧して、服もセンスのいいのを選んで着ると、仲間が皆、眼を丸くしちゃうもんねえ。むっちゃんこ綺麗よ。その店ね、お客がノーサックを指定すると、梓さんには客が回らないのよ。だから、梓さんは生でする子よりは一日に平均して一本は少ないんだって。でも、そんな高い料金の店でも、サックをつけたいというお客さんもいるからいいわと、彼女、言っていたわ。その店はサックを使うように指導めいたことを言っておいて、暗に生を迫るのだから汚いわよねえ。店のほうからお客にノーサックの子がいいかって訊くらしいわ」
「ふーん、ひどい話だ。だけどあいつならコンドーム使用を通すだろうねえ」
更に、由美が意外なことを語りだした。
私が夏美に入りだしたときの梓の反応を大層面白がって話したのだ。
「梓さんが大きな声で『ちょっと、ちょっと、由美ちゃん、ビッグニュース!、ちょっと聞いて』と言うもんで、私、一体何かなと思ったら、『由美ちゃん、××さんはこの店でもう一人通う子ができたわよ。あの様子じゃあ、その女の子を相当気に入っているみたいだけど、訊いても名前を教えてくれないのよ。いつもだったら、あの人、そんなこと、私に隠したりなんかしないのに。私でも由美ちゃんでもローザちゃんでもない女よ。あの人が名前を教えてくれないなんて、おかしいわねえ。でも、××さんが気に入りそうな子がまだこの店に残っていたのかしら?』と、また大きな声で私に言うから、この人、どうしてこんなに亢奮するのかしら?って、私、思ったわ。あの時彼女は、『一体、誰なんだろう?、ちょっと見当がつかない!』と、むっちゃんこ不思議がっていたわよ」
梓は由美と一緒になって、店の女十数人の名前を、ベテランも新人も一人一人上げ、該当しそうな女を吟味した。しかし、全くそれらしい女が思い浮かばず、「一体誰なんだ?」と、騒がしいほど怪訝がった。とにかく気持ちが落ち着かない。
パソコンの画面で調べてやろうとも思ったが、女がパソコンにさわろうとすると管理者が咎めるので、それにはなかなか手が出せないから、盛んに焦れったがった。
そのうちに、私が夏美に入ったある日、梓は、たまたまパソコンにその日の予約管理の画面が出ているのを見て、とうとう相手の女が夏美であることを知った。
梓は由美に目を丸くして報告した。
「ちょっと、由美ちゃん、わかったわよ、××さんの相手が! ねえ、一体誰だと思う? 意外よ。びっくりするわよ。夏美さんよ。それで納得したわ。意外でしょー。私、驚いた。夏美さんだとは灯台もと暗しだわ」
由美の話では、私の新規の相手が誰であるかわからなかった時も、夏美とわかった時も、梓は亢奮して、由美が唖然とするくらい大声を上げた。
梓が「意外でしょー」というのは、夏美が器量よしではなくて、サービスが悪いことでもともと定評があったからだ。
梓だけでなく私だって夏美に熱を上げることは初会の夏美の接客ぶりを考えれば全く想像できない。
「それで納得したわ」というのは、私が気に入るのが不思議ではないという意味ではなくて、私が名を伏せたのを納得したということと、もう一つ意味があった。
もともと夏美は、梓に、イクことがわからないと正直に表明していた。店でもプライベートセックスでもエクスタシーに達した経験がなかった。
男の多分九十五%は手淫で気をやることを自然に覚えるけれど、日本人の女はオナニーを覚えるのは三割以下だと言われるし、その指の刺激で落ちる味を体感しない女は、よほどセックス上手な男と情交しないと、なかなかエクスタシーの最終点まで到達することがない。
梓や由美が控え室へ戻るなり、「さっきは、××ちゃんにめろめろにされちゃって、とっても気持ち良かったわ。もう、今日はお客は取りたくない。私、寝ころんでいたい」と呟いたりすると、夏美は妬ましいような気持ちになった。
その夏美が突然絶頂感がわかるような口ぶりをするようになった。
梓が夏美に、どんな男のどのような愛撫でアクメになったのか尋ねてもとぼけていた。それで、夏美に気持ち良い経験をさせた男は、プライベートセックスの相手なのか、店の客なのか、一体誰なんだろうと、梓も由美も興味津々だった。
私が以前梓にそそのかされて夏美に入浴した時は、愛想の悪いことと性的サービスの全くないことを梓にこきおろして報告していたのに、どういうわけか殆ど二年後に、また夏美に入った。丹念なクンニリングスをして、女がイクまで愛撫をやめないから、夏美が初めて絶頂感を得たことは納得できる。
梓がそう思っただろう。
梓は控え室で夏美に「ちょっと貴女、最近綺麗になったわねえ。一体どうしたの? 女になったからかしら。ねえ貴女、女の悦びをおぼえたのじゃないの?」と冷やかした。梓に顔を覗き込まれて夏美が照れくさがっていた、と由美が言った。
私は迎賓閣の頃の梓に熱中して通った。明眸皓歯とはこの女のことを言うのかと思った。
スクリーンやブラウン管の中で見る美人と違って、頬の毛穴も見え、吐く息も顔にかかり、化粧の匂いを嗅げるような眼前の美人はどうにも狂おしい気持ちにさせる。
その梓が行方しれずになったとき、私は何とも悲しくてやるせなかった。迎賓閣ではちんぴら美少女だった梓が、恵里亜で再会するとますます美麗になっていた。
ある時心なしか梓が元気がなかったことがあって、私は、梓が寂しげに呟いた言葉が深く心に残った。
「××さんは何故そんなに私のところに来るの。××さんが梓について知っていることだけが私ではないのよ」
私は、梓が剛毅で剽軽な楽天家のポーズを取っていても、私生活は決して幸せなものではないのだろうと想像していた。
(本当の私を知ったら、貴方のようなまじめな月給取りはびっくりするわよ)
とでも言いたそうな顔を見ると、いつか、梓が個人的なことを打ち明けたらしっかり聞いてやろうと思っていた。でも、梓の、負けん気の強い独立独歩的な性格から、そんなことはなかろうという気もした。
いつぞや梓が俯いて、テーブルのガラスの面を指先でなぞりながら心のほころびをぽつりと呟いたことがあった。その時の寂しげな顔とエキゾチックな横顔の跳ねた睫毛が、私はとても印象に残っていた。
「こんな仕事、好きでやってる子なんて誰もいないわよ。皆、何か複雑な事情があるんよ」
磊落で陽気に装っている梓にしてはめずらしい情景を見せた。
「そうだろうなぁ。肉体を売るというのは大変なことだからね」
私が相づちを打つと、梓は視線を上げて強い口調で言った。
「私から見れば××さんは本当に幸せそのものの人生よ。ちゃんとした家庭に育って、ちゃんと学校へ行って、普通に結婚して、子供がいて、まっとうな仕事をして……。私たちと全然違う人生よ。××さんなんかに絶対に私たちのことがわかる筈がない!」
思い返せば、恵里亜で梓と再会してから、私は梓に勧められてよく他の女に入った。でも、その女達にもう一度入ることは全くなかった。当時の売れっ子のユカリには手違いのようなかたちで三度も会ったが、後はすべて一度きりの遊びだった。
迎賓閣でも恵里亜でも梓より本指名の多い女はいたけれど、私には梓が一番魅力的な女だった。
私が他の女に入っても、梓はそれを悔しがったり僻んだり妬いたりはしなかった。梓のそういう表情を見たかったが、その期待はむなしかった。
梓はその女達とのセックスシーンの有様を聞きたがった。私が微に細に入り昂揚の様子を説明すると、にこにこして露骨な質問を続けた。
その問に笑顔で卑猥な答を返しても、仲間の女に入浴することを梓がすねることもなく受け入れるのが腹立たしかった。梓が親しげに話をしても、気持ちを浮き立たせるような甘い態度をあまりしないから、段々もの足りなく思うようになった。
ほんのりした慕情の情緒を醸し出すような女ではないとわかっていても、いかにも「セックスプレイ」然とした情交にいつも終始していることに、どうにも抑えようのない不満を募らせた。
由美の素直でいじらしいところに心惹かれるようになると、私は、自分が心底梓のファンなのに、梓が心まで裸になっていないような気がして、惚れ甲斐がないのではないかと思うようになった。
梓は昔どこで看護婦をしていたのかも、どこで子供を産んだのかも、どういう学校生活をしていたのかも、色恋で何に苦しんだのかも、個人的な思い出や私生活の喜怒哀楽については何も話さなかった。
そういうことを私は誘導して聞き出そうとはしなかったけれども、長年親しくつきあったのだからどこかでそのような話を梓の口から聞きたかった。
私は梓の心の奥底まで手が届いていないことが残念だった。
由美の赤裸々なうち明け話に感動してから、梓に当てつけるように、由美だけでなくローザや夏美にも繰り返し入るようになった。
心から親しくなった時、女が私にどういう態度をするのか、どのくらいまでスキンシップを許すのか、それについて、その女達と梓とにはっきりした違いがあることを確認して、梓のことを恨めしく思っていた。
夏美に入るようになったとき、梓は何も動揺の顔を見せなかったが、由美の話ではかなり驚いたのだ。性の技巧を求め、面食いの私が相手にするならば、自分が夏美に負ける筈がないと思っていたからだろう。
梓が動揺したことを聞いて、私は男の矜持が修復されたような気がした。
由美は梓の動揺ぶりの想い出を語った後、語調強く言った。
「でも、あんたたち、どっちもどっちよ。素直じゃないわよ!」
由美は、私が由美に逢う度に梓のことを愚痴り、また控え室で梓が、「ちょっと由美ちゃん、聞いてよ、××さんねえ……」から始まって私のことを大声でくさすのをよく聞かされて、まるで長年連れ添った夫婦の痴話喧嘩を見ているようだったと私に言った。
由美が梓と親しいから、確かに私は由美によく梓についての愚痴をこぼした。私の愚痴が梓に伝わることを多少は期待していた。
どっちもどっちよと言うのは、二人が何かにつけて相手のことを話題にし、互いに好ましく思っているのに、いつも非難めいたことを言い合っている、と冷やかしたかったのだろう。
思い返してみると、私が由美と逢っている時もローザと逢っている時も夏美と逢っている時も、いずれも梓がニヤッと笑みを浮かべて部屋に入ってきたことが一度ずつあったが、私を見る眼はいつも射抜くような眼差しだったような気がする。
梓は、私について由美にアドバイスをしたことがあった。
「由美ちゃん、××さんに話しかけても、返事が返ってこずに無視されたと思うことがあるでしょう。それは、無視したんじゃなくて貴女の言葉が聞こえなかったのよ。××さんは結構耳が遠いから、××さんの顔が貴女のほうを向いているときに話しかけるか、声を大きくするようにしなさいよ」
由美は梓が私に充分好意を寄せていると理解していた。
見かけは客とソープ嬢との遊興の繰り返しにすぎなく、もの足りない気分になることもあったけれども、梓は梓なりに私と逢っている時には真心を見せていたに違いない。何年経っても私のことは梓の心に残り続けることだろう。
私は梓のことを思い出すと、キスシーンの情景が浮かんでこないのが不思議な気がした。あれほど親しくつきあったのに、キスを受ける梓の顔が思い出せない。キスはしていたはずだけれど、深い口づけを梓が許さないから、何も憶えていない。
思い出せるのは、私をからかったり冷やかしたりする艶麗な笑顔と、エクスタシーに浸る陶酔の顔だ。ペニスをいじくりまわす悪戯っぽい顔も忘れられない。
梓は、私が金津園の飄客となってから情交を交わした数の一番多い女だった。
梓は後年人気力士になった相撲取りを客にしたことがあった。その初土俵の年の夏に梓が相手をした。私が初めて梓に会ったのは同じ年の秋で、昭和六十三年のことだ。
最後に会ったのは、金津園の外れの産婦人科医院の前で、それが平成六年の春だ。私は四十七歳になり、その力士は大横綱になろうとしていた。
私は由美の言葉を聞いて、吉原で働いている筈の梓に想いを巡らした。
梓は別れた男から逃げているようで、金津園に戻る気配はなかった。
二度と顔を見ることはあるまいが、逢えるものなら逢って、もう一度「千手観音の梓」のゾクゾクする手淫をして貰いたいものだ、梓の哀しい人生の愚痴も聞きたいものだ、と思った。
三年間梓と痴態の限りを尽くした恵里亜は営業再開ができるのがまだ何ヶ月も先だった。 (了)
(千戸拾倍 著)