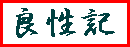
18歳未満の方は入場をご遠慮下さい。
由美3
由美は本指名を月三十本取るのに苦労することもあったが、そこそこ固定の客がついていた。ただ常連客以外の稼ぎが少ないから、それが不満で苛ついた。
痩せ細った躯は相変わらずでも、稼ぐ意欲は旺盛で、上がり部屋に飾る顔写真に効果がなくて、ちっともP指名がとれないから、由美は対策を講じようと、突然ショートカットにした。そしたらまるで雰囲気が変わった。髪の密度が薄いのが目立たず、なかなか愛らしくなった。
ロングヘアーにしていた時、私は由美の髪型が上出来だと思ったことが殆どなかった。
由美を気に入っているところは、崩れんばかりの笑顔と、純真な性格だ。涙を見せることが度々あったから、そのシーンを思い出す度に愛おしくなった。
由美は折り目正しいというか、育ちと年齢の割に一種古風なところがあった。
私が寿司を持参して由美の部屋で一緒に食事をすると、必ず「いただきます」と言い、食後は爪楊枝を差し出して、後片づけが手早い。不用な物をいつまでもテーブルの上に置いておくことがない。長年馴れ親しんだ仲なのに、遊興が終わって料金支払いの時にお辞儀をしないことが全くなかった。
仲間の女が店に来て「おはようございます」と言わないと注意した。年若でも在籍の長いボーイを年長でも入店が新しいボーイが軽く三下のように扱ったりすると、その男が由美よりもずーっと年上であろうと、在籍期間の長短を考えてものを言うように、とたしなめた。
そういう人間なのに、客の前で素っ裸でいることを好み、セックスは明るい部屋でしたいという性癖がアンバランスで良い。
由美は客に、「君、女なんだから、裸じゃなくて、バスタオルぐらい巻けよ」とか、いざベッドプレイという時に「君、部屋、暗くしないの?」と言われることがあった。
私は明るいところで交わるのが昔から好きだった。
ローザも夏美もベッドプレイになると当初は部屋を暗くしようとしたけれど、私の好みに合わせ、次第に煌々と明かりをつけたままになった。
女達はベッドプレイではライトを落とすのが普通だ。由美が接客している時ドアの窓を通して判る部屋の明かりが翳ることがないから、仲間の女が由美に、一体いつセックスしているのかと尋ねたことがあった。
「セックスする時、私、明かりなんか落とさないわ。どうして、皆暗くしてするのよ!」
そう答える由美は、私と同様、セックスは視覚による亢奮が大切だと認識していた。
由美もローザも常連客から二十万円以上の金品を贈られたことがある。ちゃっかり頂く女が多いが、由美とローザは相手をたしなめて突っ返した。
由美は私には得体の知れないところもあった。
私の前で涙を流したことが何度もあるほど純なのに、金津園に来る前に普通の会社で事務の仕事をしていた時もその前のフリーターをしていた時も、かなりの数の性交渉をした。男とベッドをともにすることで自分の存在を確認していた。
オナニー以外ではエクスタシーの経験がない時分でも、由美は恋多き女でセックス願望が強かった。
会社の男と一度だけ寝たこともあった。
仕事に厳しくてネチネチと小言を言い、女事務員たちに全く嫌われていたその男が、ホテルに誘った後は由美にだけはやけに優しくなった。由美が会社を辞めた時、男は送別会で涙を流し、記念にと言って自分のハンカチを差し出した。
男物の、しかも使っていたハンカチを貰ったってどうしようもないと思ったことを、私に愉快そうに想い出話した。
ローザは、かなり太った男が好きだ、と若い女が普通望まないことを言った。由美も、小男、禿げ親父、いかつい顔の男、そういった類に素人の時から別に嫌悪感のようなものはなかった。
由美は事務員をしていた時、取引先の男とも一過のセックスをしたことがある。三年ばかり後にその男が恵里亜にフリーで来て、何という偶然か由美の客になった。
由美はOLのときの黒縁の眼鏡をコンタクトレンズに変え、事務員時代とは容貌が様変わりしていたから男は気づかなかったけれど、由美のほうはすぐに思い出した。
うち明けると男は仰天した。想い出語りがはずんだのを切り上げてセックスを誘うと、男は性的意欲を失い、由美がどう妙技をふるっても不能状態だった。
一方では、中日ドラゴンズの熱烈なファンで、よく球場に行っていた。
由美は普通の人間がなかなか手にすることのできない、国産の裏ビデオを沢山持っていた。女の表情や上半身ばかりを写して、女のよがる声がわざとらしくて、接合部分のアップが殆どない流出ビデオ物はつまらないから見る気がしない、と女らしくないことを言う。
私が何本かを借りて見ると、確かに局部アップのシーンの多い、個性的な猥褻行為の続く、裏ビデオの歴史に残るような名作ばかりだった。
そんな裏ものが調達できるということは、由美はやくざ筋と多少の縁があるのかしらと勘ぐりたくなるけれども、由美が吉原にいた時の想い出話を聞くと、やくざと縁があるようなことは考えられなかった。
由美が吉原の店に出て何が一番嫌だったかというと、客に暴力団関係の男がとても多いことだ。恵里亜ではその手の客は殆ど相手をしたことがなかった。だから、やくざ屋さんが来ると苦痛でしょうがなかった、と顔を歪めて語った。
もう一つ、由美がまともな神経の持ち主であるとわかるのは、仲間のホスト遊びに批判的なことだった。
由美が恵里亜でデビューした頃、恵里亜の名だたる女はすべてホストに金を貢いでいる、と他店の女にまで噂になった。由美は、そんな先輩姉さん達が貢ぐ金を競い合っているのを冷ややかに眺めた。
随分心安く由美と付き合っても、もう一つ窺い知れぬところが由美にはあった。しかし、根ほり葉ほり個人的なことを聞き出すのを避けていた。自分と逢った時、由美が楽しそうにしておればそれで良かった。
恵里亜の店長は本指名を月三十本取った女に褒美として高級ブランデーを一本渡すことにしていた。
それで、由美は「私、部屋持ちの欲は出さず、取り敢えず毎月ブランデーを貰えるよう頑張るわ」と目標を決めた。
ブランデーを飲む客は私以外には殆どいなかった。たまにブランデーを欲しがる客がいると、褒美のブランデーは私の専用にしているから出さずに、フロントから店の用意している銘柄不明ものを取り寄せた。
私以外の客がブランデーを飲むのは生意気だと言った。ブランデーグラスも私専用のものを用意し、他の客には使わせなかった。
二ヶ月連続して褒美のブランデーを貰うと、部屋の備え置きは二本もいらないので私に進呈することにしていたが、その連続がなかなかなかった。
その頃の恵里亜は、検挙される前と違って月に三十本の本指名を獲得する女は四人ぐらいだった。
店の女の中では由美が最年長で、店の再開の後に入店した若い女が増えていた。ものの言い方を知らない女ばかりになって、控え室の雰囲気が暗くなったと由美は歎き、礼儀を知らない小娘たちには決して侮られたくないと真剣だった。
由美は店の男から完全にベテラン扱いされていた。
ソープ嬢になって五年目でデータが豊富だから、私は由美に、一度の入浴で男が射精する回数の分布について尋ねた。
雑誌などを見る限り二回三回とする男が多いように見えるが、私がソープ嬢から話を聞く限りでは、ヘルスと違って一回の射精で済ましている客も結構多い。
由美も一回だけで済ます客は存外多いと言い、最高記録は五回射精したのが一人だけいて、四回抜いたのはいなかった。三回抜いたのは何度か経験した。
五回抜いた男は、マットの交合で二回、ベッドの交合で二回、これがすべて女上跨位で、最後にシャワーでペニスを洗っているときに手淫を求められて、これで合計五回になり、あまりに印象的なので、随分昔のことでも相手の顔は何となく憶えていると説明した。
その男は四十代後半ぐらいで、発射してもなかなか男根が縮まなかった。その絶倫には女房も困ったようで、月に一度は奥方が金津園に行くための小遣いを亭主に渡すということだ。
「私が上になって腰を動かして、その人が出したらそんなにふにゃふにゃにならなくて、『そのまま腰を動かして!』と言われたの。(さっきマットで二回もイッたのに、この人、まだイケるの!)と驚いて、それで腰を動かしたら、そんなに時間をかけずにまたイッちゃったわ。丁度コンドームを使うようになった頃だから、私、コンドームをつけてしたんだけど、一回で随分の量を出す人だったから、二回分でコンドームの中は液体でダバダバだったわよ。それで、もう終わりだと思っていたんだけれど、またその後で石鹸つけてシャワーかけて洗っていたら、『そのまま手でこすって欲しい』と言うので、えーっ!とびっくりして、こすったの。それで、ちゃんと手で抜いたのだから、驚いたわ。その人、一度抜いても、コンドームの中のちんちんが堅いままなのよ。そういうタイプは、連続して出せるのよねぇ。でも、発射してもそのままの形でいるなんて、そんなちんちん、気持ち悪い。いや!……××さんのは、出したらあっという間に縮んじゃうから、いかにも、発射して、僕、満足しました!という感じで、私、こっちのちんちんのほうが好き!」
存外とビールが好きで、そのような想い出話をしながら、私がブランデーを飲む間に小瓶を何本か空けるようになった。
他の常連客では決してビールを飲まなかった。私が来た時は徹底的にくつろごうという気持ちだった。
私はいつも由美がビール効果で尿意を催すのを期待した。時々はタイミング良く尿意があって、そんなときは放尿ショーを楽しんだ。ラビアを開いて、奔流が排泄口を押し開けているのを凝視した。
二人とも、おしっこがしたくなると、便所へ行くことはせずに互いの目の前で生理現象を済ませた。終えると風呂の湯を手ですくって、がに股の格好で秘所にかける眺めが愉しかった。
私がそのようにしたから由美もまねた。もっとも私はがに股になる必要はない。若い女の、素っ裸のがに股姿はとにかく淫猥で、私は見てはいけないものを見た気分になった。
由美は高校一年の時まで、小便がクリトリスから出て来ると思っていた。ある時妙だなと思って鏡を前に置いておしっこをした。すると、小突起よりも随分下のほうから尿が出ているので大発見の気分だった。
友達におしっこがどこから出てくると思っているのか尋ねたら、皆見当違いをしているので正確なことを教えてやった。
そんな想い出話を聞くと、思い切りアクロバチックな格好で小便をさせ、至近距離で眺めたくなるのが私の癖だった。
恵里亜は女の在籍総数がエイズ問題が沸き上がる前の最盛期だった時期の半分の十四名程度まで減少し、その中の何人かは無断欠勤や遅刻が多くて、あてにできなかった。
手入れを受ける前に比べれば、恵里亜は美人や愛想の良い女が少なくなって、かなり客の入りが落ちた。
由美はそんな状態にいらいらしていた。
店長の渡辺は人の良さそうな腰の低い男で、ルーズな勤務をする女を厳しく躾けることが下手だった。元の店長の進藤が陰で力をふるっていたから、渡辺には権威もなかった。
渡辺が新米の女に講習をする時、由美のようなベテランを何人か呼んで指導を頼んだ。女達が新人にマットプレイの仕方を教えている間、教材のペニスを差し出すこともせずに、自分は風呂に漬かって御託を並べているだけだから、由美はあきれた。
渡辺が自らマット指導をすると、客の躯の上をヌルリスイスイと滑るものばかりで、ペニスの愛撫のやり方を具体的に教えることがない。
由美が「早く、そのちんちん、立たせて、さわり方を教えなさいよ」と言っても、萎れたままで、勃起させたことがなかった。
「何、このちんちん! 役に立たないじゃないの」
渡辺は由美達にぼろくそに言われていた。
そんな折り、進藤が店のオーナーと折り合いが悪くなり、恵里亜と縁を切ることになった。進藤は客に対しては頭が高いというか、客商売に長けているようには見えないけれども、女の統制と調達、要するに仕入れと運営が上手かった。売上は女が担当するから、それで充分だった。
進藤が採用する女は間違いがなかった。入店希望の女を喫茶店で待ち合わせて面接するとき、その女が茶髪で煙草を吸いながらだらしない格好で待って、進藤の顔を見てもまともな挨拶ができないならば、進藤は話もろくすっぽせずに採用を拒絶した。
進藤はソープランド業界に入ったのが遅くて、もともとはソープ嬢の稼ぎにたかる仕事をしていたから、同業者に陰では軽く見られることもあった。それでも負けん気を出して佳い女を集め、女達をしっかり指導し、宣伝にも工夫を凝らし、恵里亜を際立って繁盛させた。
だから、由美は進藤を応援したい気持ちがあったし、また、その手腕を高く買っていた。
進藤はなかなか男前で、苦み走った顔に男っぽさが漂っているから、店の女も進藤にポーッとすることがあった。指導方針が明確で厳しく、女達からは畏敬やら憧憬やらの眼で見られた。
由美は恵里亜に入った時に進藤の講習を受けた。ところが当日はまだ生理中で、タンポンの紐を垂らしたまま指導を受け、進藤とセックスをすることもなかった。
控え室に戻ると、姐さん達が、進藤とやったかと冷やかし、由美が、生理中だからエッチはしていないと答えると、姐さん達が驚いた。
「ちょっと、あんた。あの進藤さんと、あんた、タンポンの紐ぶら下げてみっともない格好で講習を受けたの? そりゃあ、あんたが、初めてよ」
それを聞いて由美はどうにも恥ずかしい気持ちに襲われた。
進藤が由美に、恵里亜を出ることを内緒でうち明け、ついてくることを頼んだ時、由美は承諾した。しかし、進藤が恵里亜と別のグループの店の責任者におさまっても、由美に声をかけることはなかった。由美はそのことに失望した。
そればかりか、進藤が恵里亜と渡辺の悪口を言い散らしている、と聞き込んで腹を立てた。好人物の渡辺を何としてでももり立てようという気になった。
渡辺のほうも、由美が女の中で最年長だから、女のことでは何かにつけて由美を頼った。
ローザがヴィーナスから復帰してしばらくは由美と別の班で、二人の出勤日は殆ど重ならなかった。渡辺が班編制を変えると言ったとき、由美もローザも二人が同じ班になるようにして欲しいと訴えた。
その話を聞いて、私は嬉しくない話だと思った。
由美に逢えばそれがローザにすぐ判るし、ローザに逢えばこれも由美にすぐに判る。ローザに逢っているときに由美が男とセックスしているのは不愉快だし、由美を抱いているときにローザが男に愛想を言っているのを想像するのは面白くない。
結局二人は同じ班にはならなかったが、月に十日前後は出勤が一緒になることになった。
由美は、店が再開した後の新しい仲間が、昔の仲間と比べればまるで礼儀知らずで、お澄まし屋で、無口な女が多いから、控え室はいつも陰気で暗いし、話し相手がいなくてとてもつまらない、と私に愚痴った。ローザも全く同じことを言った。
もともと恵里亜は進藤の指導がしっかりしていて、部屋持ちの女でも部屋に籠りっ切りということはなくて、控え室で皆と一緒に客待ちした。
進藤が性格に問題のない女だけを採用していたからだろうが、私から見ても女達は大変仲が良かった。女同士のトラブルがあまりなく、昔は、気の合った仲間で旅行もよくしたし、皆で陰部の見せ合いっこなんかもしていた。そんな控え室の雰囲気を、由美もローザも懐かしんでいた。
女達が親密で、天衣無縫ぶりを競い合ったことは、由美から、店が検挙されたときの想い出話を聞いて私もよく判った。
警察が恵里亜に踏み込んだ日に店に出ていた女は当日取調を受けた。
由美を含め非番の女は翌日出頭して調書を取られたが、長く店にいる女は五時間ぐらい聴取を受けた。取調を受けるのは初めての女ばかりなのに、萎れているのも泣きそうな顔をしているのも一人もいない。
灰皿を要求して皆スパスパしているし、「のどが渇いたわ。何か飲ませてよ。……お茶? コーヒーかジュースでもないの?」とか、「おなか、へったわ。何も出ないの、こんなに引き留めて。何か食べさせてよ」とか、「長いわねえ。いつまでするのよ。さっさと聞きたいこと、聞いてよ」と不平を言い放題で、挙げ句の果てに、調書の記入ミスがないように慎重に記録作業をしている取調官を「ほんとに書くのが遅いわねえ」と皆で冷やかしている。
警察が食事を出すと、「何!、吉野家の牛丼! 何だ、カツ丼じゃないの。しけてるー」と不平を言う。調書に添付する写真をポラロイドで撮る段になると、「ちょっと待って!」と言って、雑誌の写真を撮るように入念な化粧をして微笑みを浮かべてポーズを取るのや、ピースの指サインを出してニコニコ顔で写るのやで、爆笑の大騒ぎだ。
取調をした男達も、「今まで金津園の女を随分相手にしてきたけど、お前達のような言いたい放題なのは初めてだ。恵里亜の女は本当にすごいなぁ」とあきれた。
「あなた達、こういうことしていても男なんだから、やりたくなったときは金津園に来るんでしょう。正直に言いなさいよぉ。上司には黙っているからぁ」
さんざん冷やかし、男達が照れた顔で頷くと、「ねえねえ、教えて、どこの店? 誰に入ったの? きれいだった?」で、また大爆笑だった。
私は、警察の検挙を受ける前の、梓も夏美もローザも皆恵里亜にいた頃は、さぞや控え室がにぎやかだったろうと想像した。
平成八年十月にローザがソープから上がった。平成九年の二月には、私は夏美に通うのをやめた。
由美だけが私の通う女になった。
その頃まで私はダブルの時間で遊んだことが一度もなかった。射精が一度しかできないし、会話がとぎれるのはどうも面白くないから長い時間で遊びたいとはあまり思わなかった。
ところがひょんなことから由美とダブルで遊ぶことになった。そんな長い時間由美と一緒にいるのがとても嬉しくて愉しくて、結局二百分の間にヘネシーを三合以上ロックで飲んでしまい、正体不明なまでに酔っ払った。
由美がビール小瓶を軽く四本空け、私のペースよりも段違いに早いから煽られてしまったし、何よりもその日の由美の笑顔がいつもよりも素晴らしいように思った。
もともと由美はそれほどお喋りではないのに、その時は饒舌になって、私が最も好奇心のある、個人的な想い出話をするから、精神的に宙を漂うような気分だった。
結局私は脳味噌が先にエクスタシーに達して、勃起不全に至り、由美に申し訳のないような長い手淫をさせて何とか吐精を果たした。その後は家にたどり着くまで完全に酩酊の状態で、JRの列車とタクシーの中で必死に睡魔や嘔吐感と戦う羽目になった。
時間が長く取れる時、最初風呂に入る前に由美と交わるようになった。
由美は他の客では股間を洗浄する前にセックスに応じることは滅多になかった。私が相手の時は別で、にっこり笑ってベッドに上がり、膝を立てて股を開いた。何せ前戯抜きだから膣に湿り気がなくて、唾を塗りつけたペニスが入り口の膣壁を引っ張って押し入る感触が良かった。
クンニリングスで気をやらせて、割れ目がべとべとになっているのも風情があるけれど、いつもそればっかりだから、濡れていない肉壺に挿入するのもいいものだと思った。
嵌め入れようとしてもペニスの裏筋が引っ張られて具合が悪い。一旦抜いて、先走り汁をカリ首に塗りつけ、指で割れ目をしっかり開いて再度挿入してもつるりと没入せず、ペニスが膣口の皮膚を牽引したまま奥に進んで頼りない状態になる。
それを二人で顔を見合わせて笑うのもなかなか愉しいと思った。
やがて膣は湿りを帯び、ペニスの動きが滑らかになる。最初の交合では射精するつもりがないから、いつも長く抽送を続けることができた。
私は女上跨位や側臥位やその他の変形体位を好まないから、いつも私が上になり、対面の形のいくつかの体勢でかかってゆったりとピストンを続けた。正上位と後背位、足を伸ばしたのと曲げたの、それに上体の構え方、その組み合わせでかなりの数の体位が可能になり、嵌め込む角度と眺めを愉しんだ。
肉壺がしっかり潤うと、由美は目を開けたまま笑みを浮かべて突き込みを受ける。由美がいつも抽送を愉しむ顔をしているから、私は幸せな気分になる。
私は特に、腰を使いながらキスをするのが一番好きだった。
気をやりそうになったところでペニスを抜き、突いて突きまくった肉孔が丸く開口しているのを毎度眺めて喜んだ。抽送を長く続ければ、陰裂を開かなくてもペニスが嵌まっていた丸い形状が必ず確かめられた。形状記憶合金という言葉を思い出した。
由美に逢うようになって五年目に入った。由美の躯は見かけも生理的にも二十二、三の頃から随分変わった。顔が丸くなり、腿や腰に脂肪がのって女らしくなっただけでなく、エクスタシーの最高点へ到達するまでの時間が長くなった。
昔の由美は、弱い口唇愛撫でもしっかり続ければあっさりイッたが、二十七歳のその頃には、私はかなり時間をかけて強く女芯を愛撫するようになった。その分、浅いエクスタシーが深々としたオーガズムに変わった、と由美が言った。
ラブジュースも粘りっけの少ないものから、糸を引く、接着剤のようにとろみのある粘液になった。そんな由美の肉体の変化が私は面白かった。
それに、由美はクンニリングスの好みがいつの間にか変わった。
以前は、クリトリスを舌先で縦に刺激する、つまり、下のほうからすくい上げるようにはたくと、由美は過敏な反応を示し、こそばゆくて腰が逃げた。舌の上下の動きではなく、舌面でクリトリスを軽く包み、そのまま顔を左右に揺すって横方向にバイブレーションをかけると、由美は非常に具合がいいようだった。
ところが、いつの間にか、舌面をクリトリスに押し当てて横方向に揺さぶるのは、腰を引いてしまうほど刺激を感じるようになり、舌先で上下にはたかれるのを好むようになった。
女のオナニーは、指先をクリトリスに当てて左右にゆらゆらと動かすやり方が普通だ。由美はソープにくる前は頻繁にオナニーをしていたから、その名残で、二十代前半は横方向の刺激を好み、後半は、ソープ稼業のおかげでクリトリスが成長して縦方向の刺激がよくなり、左右に揺すられるのは耐えられぬ強い刺激になったのではないかと思った。
そのことを由美に言うと同感した。
警察の手入れを受ける前店の女達は皆奔放に過ごしていた。全員の第二次性徴の発達ぶりを比べ合ったことがある。乳首を刺激して勃たせてからサイズを確かめた。皆で割れ目の長さやクリトリスの大きさを比較した。
由美は店の姐さんたちと一緒に風呂に入った時、浴槽の縁に座らされ、梓に性器を観察された。
梓は、店の女の中で由美のクリトリスの大きさが二番目だと感心した。
「由美ちゃん、あんたのお豆さん、しっかり剥けているわ。これだけ大きくてしっかりとび出ているのは、そうはいないよ。これいいわ。あんた、この大きさはヒカルちゃんの次だわ。立派。男だったら巨根でつる剥け、黒光り、エラの張った見事なおちんちんだよ、これは。みんな、クリトリスを剥いても、これだけ中身は出てこない。あんた、相当オナニーしていたんでしょう? 正直に言いなさい。そうとう手まんこをしなきぁ、これだけ豆がとび出ない」
ヒカルちゃんというのはAVに出たことのある女で、見事なサイズのクリトリスの持ち主だ。で、確かに由美のクリトリスは、私が相手をした女の中でも、クリトリスを唇で包み込むことのしやすさ、クンニリングスのしやすさという点で、ローザと並んで双璧だった。
憩いという漢字は、自と舌と心の三つの合成だ。
自分の舌で愉しむ心が憩いとはよくできていて、他人の舌で愉しむフェラチオよりも、自分の舌で愉しむクンニリングスのほうがまさしく憩いとは、素晴らしい漢字だと私は考えた。
「今、変なイキ方をしちゃった!」
由美はこんな言い方を時々した。
変なイキ方とは、もうすぐ気をやりそうだという予感がないままいきなりアクメに至ることをいうのだ。徐々に昂まって、もうすぐイキそうだと究極の快感を待ち望んでいるところで、ズドーンとエクスタシーの頂点に登りつめるようなイキ方ができなかった時によく呟いた。
たとえば、由美が生理前後の時は、私のクンニリングスから受ける刺激が、快感と感ずるよりも先にくすぐったくてしょうがなくて、くすぐったいのをこらえているうちに、まるで失禁するようにずるずると頂点に到達してしまうことがあった。
それが変なイキ方で、アクメの究極を目指して階段を上っていくような感覚がないから「イキそう!」と悶絶して叫ぶ予告がなかった。
そんなとき、私は不完全燃焼のクンニリングスをした気分になった。
由美がやたらくすぐったがってピクピクするから、かなりソフトタッチで舐めなければならない。あまりに軽い接触だから遊んでいるようなもので、刺激している気がしない。それで、アクメへの到達はまだ先だろうと思っているうちに、由美は気をやってしまう。
快感が浅い場合もあれば、正常のイキ方と同様に深い充足感を得られる時もあった。
変なイキ方をした時でも、たまに、由美はよがりぶりを全身で表し、達した後のうつろな顔が何ともエロチックなことがあった。
私はクンニリングスとフェラチオを互いにし合う69がとても好きだけれども、由美とはそれをしたことがなかった。ローザとも殆ど69をしていない。ローザも由美も相互オーラルをいやがったからだ。
二人とも、私にクンニリングスされているときにフェラチオしても、せっかくの素晴らしいクンニリングスに集中できないし、わがままを言わせてもらえば、気持ちがいい時にペニスを咥えたくないと言う。
そのセックス哲学は、私には嬉しくないが、クリトリスの感覚を味わうことに集中したいという気持ちもわかるので、69を無理にやらせたことはなかった。
由美のクリトリスを愛撫するときは同時にペニスを愛撫されることがないので、私も、女の昂揚ぶりを観察しながら、ひたすらクンニリングスすることに没頭できた。
69は女のよがる顔が見えない不都合があるから、同時双方向のオーラルセックスだけが最高のセックスというわけでもあるまい、そう思って不満を抑えた。
由美の膣口に三角錐の形をしたピンクの肉が上下に飛び出していた。小鳥のくちばしのように見えることがあり、由美は「エイリアンの口みたい」とよく呟いた。
私は、舐め尽くして、由美が気をやると、濡れた陰裂を必ず鑑賞した。クリトリスが肥大し、エイリアンの口も飛び出し、小便の穴のまわりの肉色の壁も内側から押されるように膨らんでいるのを確認した。
その猥褻なさまを見て自然に勃起させるのが私の狙いだった。
(由美の、濡れて膨らんだおまんφはとても楽しいけれど、もうちょっとエロっぽい匂いがあったら最高なんだがなぁ)
そんな贅沢を思い浮かべた。
由美と合体すると、私は時々由美に「ハァー、してぇ」と言うことがあった。
由美の口許に顔を近づけて、吐く息を浴びるのが愉しかった。全く口臭のない、さわやかな息だった。恥ずかしそうに微笑む顔に、毎度たまらない想いがした。
長く女と付き合うのは、まだ大人になりきってなかった女の肉体が爛熟していく過程を充分に確認できるし、また、私が壮年から初老へ階段を上りかけて、精力の衰えを見せていることを二人で話のネタにして、仕事のストレスでペニスが不如意の時でも、ベッドでじゃれ合っているうちに何とか勃起を果たすことができるから、なかなか愉快なものだ、と思った。
ローザがいなくなったのをとにかく惜しんだが、その喪失感を埋める以上の親愛の情を由美が見せるのがとても嬉しかった。
ローザがいなくなって三ヶ月が過ぎた頃、由美は部屋持ちに昇格した。ローザの常連客の何人かが由美に回ったことが奏功した。
昇格は二度目で、一度目は随分昔、私が由美に通いだして四ヶ月目のことだった。由美は店の女の中で年齢は二番目、在籍が最長で、女達のまとめ役を務めていたから、部屋持ちの名誉を得たことは面目をほどこした。
P指名を含めれば由美よりも稼ぐ女は何人かいたが、ローザがいなくなって、本指名は由美がトップになることが続き、一月という繁盛する月に、由美はいつもよりも本指名数を稼ぎ、部屋持ちになることができたのだ。
初めて部屋持ちになった時は、その資格が二ヶ月くらいしか続かなかったので、今度も特別待遇を何ヶ月も続ける自信がないから有り難迷惑だと言うが、やはり表情は晴々していた。
私は、由美から金が稼げない愚痴を聞くよりは、由美がいろんな男を相手にしてその報告を聞くほうが愉しいので、一層客の心を掴むように激励した。
話がとぎれた時に、由美が時々十代の頃の想い出語りをするのが楽しかった。
由美は中学生の時柔道部にいた。なかなか強くて大会にも出たことがあった。高校に入った時もう柔道をする気は全くなかったが、入学式の直後から入部をしつこく誘われた。
あまりの熱烈な要請に、顔だけ出そうかと思って練習風景を見ていたら、由美の眼にはまるでお嬢さんのダンスのように見えた。これならたいしたことはないなという冷ややかな顔をしたので、試しに柔道着を着るように求められてしまった。
最初に相手をした女からあっさり一本をとったら、三年生の一番強い、どうも主将らしいのが出てきた。新入生を相手に力を入れた応対で驚き、すぐ負けるだろうと思ったら、その相手にも簡単に勝った。
主将の姉さんにも顧問の先生にも入部を懇願されて、お嬢さんのダンスの仲間に加わる気はなかったけれど、試合に出ることぐらいは協力することを承諾した。
結局由美は殆ど練習には参加せず、一年生なのに対外試合では大将で出場していた。
由美は肩から上腕にかけて筋肉がついて、逞しいと言っていいぐらいで、上腕部は、スポーツを全くしない私よりも太かったし、腕力も私よりもあった。
由美がマットの支度をしていると、風呂に浸かって由美の後ろ姿を眺めていた客が、「君、何かスポーツをやっていたの?」と尋ねることが多かった。
由美は高校を卒業するまでは処女を守っていたし、成績もまあまあだった。そんな由美が高校を出るとセックスをしまくるようになったのが、何とも興味深い。
相手はかなり年上の男が多く、既婚の男と恋に落ちて同棲したこともあった。女房に駆け落ちされた父親が、紡績工場の女工をよく引っかけていて、そういうのを子供の頃から見ているから、セックスに処女の時分から興味を持っていたのだろう。
私は由美に通い始めた頃、由美から、かなり年輩の男と寝たことがあると聞いたことがあった。
飲み屋で会って意気投合したセックス上手の小父さんで、由美の口ぶりでは、一度や二度のセックス回数ではなさそうだが、長くてもせいぜい数ヶ月の一過性のつき合いだろうと思っていた。
その男のことを私は殆ど忘れていたが、由美と一層親しくなってから時折プライベートセックスについて尋ねると、その小父さん、というよりは爺さんが、由美が女房持ちの男に失恋して心の闇にさまよっていた時、自暴自棄の心を支えてくれた恩人だった。
それだけでなく、由美が店の仕事のセックスを除けば一番多く寝た男だった。
由美は二十歳でもセックス経験は豊富だったけれど、爺さんと寝て、丹念にクリトリスを刺激される絶妙のクンニリングスを初めて味わい、奈落の底に沈んでいくようなエクスタシーを感じた。これが本当のセックスだと感動した。
まだ由美が金津園に出る前、一時期二人は週に何度も関係を結んだ。爺さんは熟達者で由美が驚くくらい様々な体位で交わった。バイブレーターをクリトリスに当てられて登りつめたこともあった。
由美がソープ嬢になってからもつき合いは続き、爺さんが入院すれば、好物を持って何度も見舞いに行った。還暦をとうに過ぎたその頃は糖尿病を患って、もう性的意欲を失い、一緒に酒を飲む程度のつき合いだと由美が説明した。
その爺さんが由美の惚れている愛人だと夏美が思って、その話を聞いて由美に嫉妬したことがあった。
男には内縁の妻がいて、それは由美が勤め帰りに行きつけにしていた飲み屋のママさんだった。その婦人とその男との三人で遊んだこともあった。若い由美に対し倍に近い年齢の小母さんと、クンニリングスをして互いに気をやらせてしまうという本格的なレスビアンプレイをした。
由美は小母さんにクンニリングスをされたらすぐにイッてしまうのに、自分が小母さんにクンニリングスすると、とにかくイカせるまで時間がかかって、口や顎が疲れてしまい、うんざりすることもあったと想い出を語った。
小母さんのクリトリスはめり込んでいて舐めにくく、途中で指のマッサージに代えると不満を言われるから、由美は往生した。
熟女の峠を越えた歳なのに、割れ目が何だかやけにくさいからイヤだったけれども、とにかくクリトリスを舐められるのが大好きな小母さんで、我慢してクンニリングスをした。
爺さんがバイブレーターをあれこれと持ってくるので、由美は小母さんと二人で一緒に試用し、それを爺さんに見せて愉しませていた。
それなら由美はバイブレーターが大好きなのかと思い、クリトリスの刺激に良さそうなものを一本買って店まで持ってこようか、と打診すると、器具はやっぱり性に合わない、刺激が強すぎるし痛い、と言う。
由美と爺さんと小母さんの三人でスキーに行った時の写真を並べたアルバムを由美が店まで持ってきたことがあった。
私は、まるで家族旅行のような写真を見たり、爺さんが由美と性交をするときは、たとえ安全日でも必ずコンドームを使ったとか、舐められている時に尿意を訴えると、爺さんにそのまま出せと言われて口の中に排尿したなどと由美から想い出話を聞いたりすると、由美の常人とはちょっと違う個性に何とも惹かれた。
私は由美にヒモがついていないことにほっとした。
由美が金津園に出るようになったのは、まだ金津園のソープ店が何をするところか知らない時、行きつけのスナックのマスターに、「セックスが大好きな由美ちゃんなら、金津園はぴったりの仕事だよ。お金はしっかり稼げるし」と勧められたからだった。
由美の想い出話で毎度大仰な顔で声も高くして語るのは、由美が二十一で恵里亜に入店し、初めて出勤して控え室の女達の顔を見て驚いたことだった。
梓も含めて五人ばかり超一級の美人がいて、これは場違いのところへ来てしまった、自分のような並の器量から少し超えた程度の女を店はよくぞ採用したなぁ、と愕然としたのだ。
私はそのうち三人に入浴したことがあるが、確かに由美が挙げた五人は超弩級の別嬪だった。でも、由美が女達の取りまとめ役を果たしているその頃は、店の女の中で由美が一番美人だと私は思っていた。
由美とローザと夏美の三人に毎月通っていた時、私は三人の性格の違い、カリ首などを愛撫する時の仕草と表情の違い、愛撫のされ方の好みの微妙な差、三者三様のエクスタシーの違いを観察して愉しんでいた。
残念なことにローザと夏美には逢うことがなくなり、そのような面白みはなくなった。
だから私は恵里亜でローザや夏美に代わる女がいないだろうかと考えたが、由美一人で充分とすべきだろうとも思った。
ある日私の心がとろけることを由美が言った。
交合が済んで、由美がティッシュで割れ目を拭った後、なかなかシャワーで洗わずにそのまま会話につき合っていることに気がついて、私がそれを指摘すると由美が答えた。
「私、××さん以外の男だったら、発射したらすぐ体を離して、シャワーのところへ飛んで行くわ。いつもそうよ。必ずゴムを使っていても、すぐにそうしないと我慢できないの。気持ち悪くて。でも、××さんなら、汚いとか思うことはないし、私、自然にしていたいわ」
私が気をやった後、由美は洗浄もせぬまま最前の深いアクメとアルコールの効き目で、そのままいびきをかいて寝入ってしまうことがあった。
(由美は完全に心を許している!)
そう思うと私は人生が楽しくなる。
かすかないびきと時折配管を通る排水の音がなければ、静寂と言ってもいい恵里亜の一室で、私は由美の躯の熱を肌で感じながら、煙草を吸おうかどうしたものかとためらった。
(体を動かせば由美の目が覚めるのではないか。由美のまどろみと腕枕のしびれがかけがえのない愉しみの帰着するところならば、できるだけじっとしてこいつのいびきに耳を傾けているべきだろう)
由美はなかなかソープから足を洗いそうになかった。一体どれくらい付き合うことになるのかな、と私は感慨深く由美の顔を眺めた。 (了)
(千戸拾倍 著)