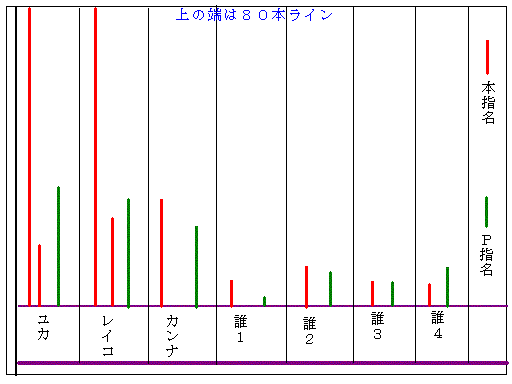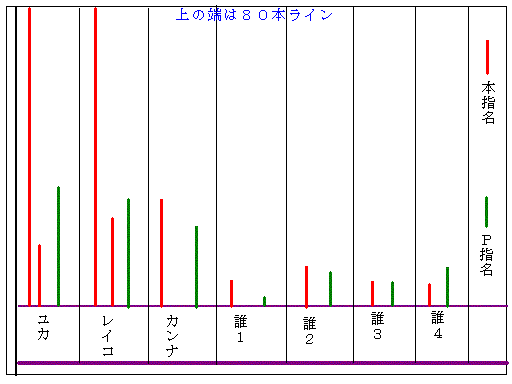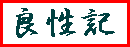
18歳未満の方は入場をご遠慮下さい。
あるソープ嬢の想い出(後編)
5.ショック
入店してしばらくの間は無我夢中で過ごしていた。朝、ボーイさんたちに顔を合わせる時、控え室で仲間と一緒にいる時。何を怖がっていたのかはわからないけれど、お客さんを相手にしていない時間で、私はカチンカチンになっていた。
はじめて社会人になった時もそうだったけれど、新しい集団の中に入る時、私は無性に不安になる。変な奴だと思われないか、一人だけ雰囲気が違っていて、それを理由に反感を買わないかなど、気分は転校生だ。
ソープで働く人たちとは、私にとっては全く未知の世界の人だったから、控え室にいる、何ら自分とは変わらない女の子を見ても、どこかで警戒していた。
お店の控え室はとっても広くて、常に十人以上の女の子がいた。普段は食事をしたり、ボーッとテレビを眺めたり、雑誌をめくったり、好きなことをしている。
ただ、それだけ人数が多いと、やはり仲良しグループができる。
誰か一人、それまで話に加わっていた子が席を外したとたん、その子の悪口大会が始まったりする。
これには閉口し、がっかりした。同時に、自分がどう思われているのか気になって仕方なくなる。控え室ではいつもニコニコ、実は内心ピリピリしていた。
こんな状態だから、私にとってお客さんにつくということは、仕事というよりも、窮屈な状態からの解放になった。
たまたまだったのか、私がなれぬマットプレイを頑張って、ベッドプレイもそれなりにこなして、適当に話を合わせておれば、文句を言わずに帰っていくお客さんばかりだった。
サラリーマンの営業成績をつけるみたいに、指名数のグラフが控え室に貼ってあった。No.1とNo.2の位置が随分高くて、後の大多数はドングリの背比べ。だから、あまり気にならなかった。
大体、フリーの客が多いから、指名客を持っていようがいまいが、あんまり関係ない。指名客をもっと増やさねばという意識も全くなかった。この人をもう一度返そうという意識ではなく、クレームが出ないようにして帰ってもらおうという気持ちだった。
マットを習った時と同じ。(私、指名なんて返せませんから。そんなに高望みなんてしていませんよ)という考えだ。今思えば恥ずかしい限りだが、こんな考えで私はずーっと働いていた。
個室は控え室からの解放だった。自分の周りの人間はとりあえず一人だけになる。その一人は、皆セックスしたくて来る男なんだから、おとなしく体を与えておけば文句はないはず。
こんな考えを貫いた。一緒に気持ちよくなるとか、一緒に愉しむとかのものではないと思っていた。
多分、心から楽しいと思える客に当たらなかったことも原因だ。この百分を過ごせばお金がもらえるわと、プロ意識にかけていた。
私にとっては、見知らぬ男と、会ってすぐに寝てあげたことそのものが、すっごい大仕事であり、もうしっかりサービス料に見合っていて、その上何かしてやろうという気は起きなかった。
こんな状態だから、自分自身を今一度省みるのは少し後になってからだった。
不幸なことに、ついたお客は皆「明るくていいね」とか何とか私のことを褒めはしても、クレームをつけることはなかったようだ。褒められる度に私は安心した。
(あぁ、やっぱりこんな感じの接客でいいんだ)
他の子がもっとひどかったのだろうか。今となってはわからない。指名も取れるようになってきて、テクニックも一皮剥けた今のほうが、よっぽどお客さんに文句を言われることが多い。納得いかない。
とにかく、あまりに何も言われず、また、接客中は控え室にいる時より居心地がいいから、たとえば真っ先に感じるべきであった羞恥心は、今振り返ると殆ど感じていなかったようだ。
私は、プライベートなつきあいの中で、あまり女の子として扱われていなかったような気がする。
男友達も多い。その何人かと、女の子は私一人というメンバーで飲みに行き、誰かの家で皆で雑魚寝という経験も何度かあった。
会社員の時だってそうだ。女子社員にはちょっとと思うようなきつい仕事をやらされたし、男の中に普通に交じって、良くも悪くも女らしさとは無縁だった。
それがソープランドともなれば、こんな私でも女に見えるらしい。
皆が私を「アイちゃん」とちゃん付けで呼んでくれる。
私の乳房を見て目を丸くし、「カワイイねえ。彼氏、いるの?」なんて聞いてくる。考えてみれば、ここまで女を武器にした仕事もそうはないだろうから、当たり前の話なのだが最初はからかわれているのかと思った。
「おっぱい、大きいねえ!」→うっそお?
「カワイイねえ」→思ってもないこと言うな!
「彼氏、いるの?」→いるように見えるかぁ、何を聞くんだ、こいつは!
等々、女である部分を褒められれば褒められるほど、心はひねくれていく。
自分の、女としての体を買われていくと考えたからかもしれない。考えすぎだ。単純に楽しみに来ている人には、いい迷惑だろう。
私は、お店に面接に来た時は、泣き出しそうなほど恥ずかしい思いだった。こんな私ですいませんが……という態度だった。
即座に力強く「大丈夫だよ、平気だよ」とフォローしてもらえたため、入店した時点で、申し訳ない気持ちはどこかへ行ってしまった。店が私をよしとしたのだから。
だから、私は自分の容姿のコンプレックスのことをしばらく忘れていた。
でも、いろんなお客さんにいろんなことを言われて、それで少しずつコンプレックスのことを引き出していった。そういえば、私は売り物にならないくらい、恥ずかしく太っているということを。
何週間も経ってから、風変わりな客についた。
ぼそぼそ喋って、無表情。ちっとも楽しそうじゃない。マットプレイは多分やったと思うけれど、よく憶えていない。
ベッドプレイに入ると、無言で私の上にのしかかってきたから、(よし、マグロじゃないな。受け身でいればいいから、楽だなぁ)などと思いつつ、任せた。
その人は結構熱心に攻めてくれたので、気持ちよかった。だから、終わった後で、私は正直に「気持ちよかった」と言った。
すると、その人は、深くため息をついて、「あーぁ、どっちが客だか」と言った。
ものすごくびっくりした。
攻めたいから攻めていたんじゃないのか? 仕方なしだったんだろうか?
それまで本気で乱れていたのが、すごく恥ずかしくなった。
そして男は、帰り際、お金を渡しながら言った。
「気持ちいい思いをさせてあげた僕が、こうしてお金までやって……君って、いい仕事しているよねえ」
ショックだった。無理して相手に合わせてプレイしていた子なら、こう言われたら怒り出すだろう。けれど、私は本気で楽しかっただけに、悲しくなってしまった。そして次に、猛烈に恥ずかしくなった。
ベッドで頑張っても不思議とイカなかったり、中折れしてしまったりと、うまく事が運ばない時もあるにはある。でもこの頃はそういう経験がなかったため、股さえ開いておれば、何も文句を言われることはないと思っていた。
ましてや自分の「素」をさらけ出したのに、それを醒めた目で見られていたのかと思うと、実にこっ恥ずかしかった。
その時から、私は受け身のプレイが嫌になった。
マットプレイの時のように、自分がせっせと動いていればいい。そう考えても、ベッドで女が主導権を握るって、一体どう動けばいいのだろう。全くわからない。
控え室で先輩姉さんに、「ベッドで受け身になる以外に、どうやって攻めたらいいんですか?」と聞いてみた。
「そんなこと、気にしなくていいのよ。まだ、新人なんだから、お客さんに甘えて、おまかせにしたほうが、初々しくていいじゃない」
と笑われてしまった。
それが恥ずかしいから聞いているのだけれど、あんまり張り切っていると思われるのも嫌だったので、それ以上追求するのはやめた。
ソープ嬢のくせに「受け身で乱れるのが恥ずかしい」なんて、誰にも言えなかった。
しばらく経ってから、五十代の小父さんがやって来た。
この年代の人はあまり接したことがないけれど、お客さんとしては安心だ。優しい人が多いし、もし受け身の時にすごく感じてしまっても、ちゃんと喜んでくれることが多いからだ。
いつものように接客を始めた。可愛く振る舞うことにもなれてきた。無理矢理かわいこぶっているわけではないが、素直にセックスできるのは楽しかった。
ところが、その小父さんはちょっと変わっていた。妻の他に、二十二歳の愛人がいるらしい。私と同じ歳だ。で、話は殆どその愛人のことだった。要するにのろけ話だ。
彼の言によれば、その子は、結婚を望まず、奥さんと別れることも望まず、今のように週に何日か逢えればいいと言う。
そういうことを話している間にも、彼の電話にはその子からメールが入った。
“今、会社から帰ってきたよ〜”
“ちょっとコンビニに行ってから、お風呂に入って、寝まーす”
彼はその度にメールを私に見せては、眼を細めた。
「かわいいだろ? ちょっとしたことでも、こうやって僕に報告してくるんだ。まっとうな仕事してて、うるさいこと言わないし、家庭もこわす気はないらしいし」
(えーっ、うそだっ)
同じ歳の女として言わせてもらえば、どれかがうそだろう。
本気で相手のことを好きだったなら、将来だって考えて欲しいだろうし、そう言わないだけじゃないだろうか? 大体この人、奥さんがいて、愛人がいて、そのことをソープに来てのろけ、何なんだろう。
かなり反感を持ったが、そんなことを主張する権利もなかろうと、私は聞き役になっていた。全く興味がない話だし、はっきり言って気分が悪いが、ひたすら「ふーん」と相槌を打っていた。
やっと百分経った。まだまだ続きそうなのろけ話を制した。
そして、帰り際に小父さんが言った。
「本当にかわいい子なんだねえ。美人でスタイルもいいし。ソープで働かせたら、ナンバーワン間違いなしだよ、僕が許さんけどね。……君みたいな子でもソープ嬢で通るなら、僕の彼女なんかもったいなくてこんなところで働かせられないよ。……じゃ、また。せめてもう少し痩せた方がいいよ」
ガーン、なんてものではなかった。
その男が何を言ったのか、丸一日くらいはわからなかった。
私は比べられていたみたいだ。美人でスタイルがよく、尽くす愛人。ブスで、太った、ニコニコするだけのソープ嬢。
そりゃあ一言言いたくなるのもわかる。悲しくなってきた。
入店したての頃のあの気持ちがはっきりと蘇った。
そうだ、私はものすごくスタイルが悪かったんだ。こんな体型で、通用するはずがなかったんだ。顔から火が出るほど恥ずかしかったし、それを通り越して本当に悲しかった。
次からが大変だった。
スタンバイがかかって、お客を迎え入れる。客が皆、私の体の太さに釘付けになっているような気がする。
「うわっ、すごいデブだ。最悪ッ!」と思っているに違いない。
「カワイイ」と言われても、見えすいたお世辞を言うな!とばかりに鼻で笑ってしまう始末。店に出る時も周囲の目が気になって仕方がない。見て見て、あんな太い女がいるんだよ、あの店は、などと思われていないだろうか。
消えてしまいたいって、こういう心境で使う言葉だろうか。
存在自体が恥ずかしい。いたたまれない。客の目をまっすぐに見られない。
部屋の電気を暗くするようになった。
以前先輩の姉さんのすぐ後に同じ部屋を使った時、殆ど真っ暗にしてあったことがあった。ああなるほど、こうすれば、お互い恥ずかしくないし、太った体を見られて嫌な思いをすることもないなと思った。
仕事を始めて、最初は夢中だったけれど、周りが見えてくると、自分も見えてくる。すると、(私って、こんなに不細工なくせに、何やってんだろう?)と思うのだった。
控え室の女の子を見まわしてみる。いつも十人以上はいる。太っているのも痩せているのもいろいろだが、いわゆるスタイルの良い子はあんまりいない。
しかし、私より明らかに太っていると思える子も一人しかいない。しかし、その人はベテランだし、一向に気にしていない様子だった。
とにかく痩せなきぁ。
6.仲間
夕方の5時くらいになると、控え室にいる女の子たちは一斉に出前の注文で電話をかけ始める。この時間帯は帰宅ラッシュに当たるので、比較的に夕食をとりやすいのだ。みんな機械的に、面倒くさくなさそうなお弁当を注文し、食べる。
仕事が苦痛で、つまらなくて仕方ない私には、この食事の時間が唯一の楽しみだった。
おかしなことに、「自分は太っているから、痩せなくちゃ」と意識しだした瞬間から、体重はむしろ少しずつ増え始めていた。
ストレス太りというものが本当にあるとしたら、その時の私がまさしくそれだ。
けれど、何か嫌なことを心に抱いている時に、やつれていかないと周りは同情してくれないから、おかしな話だ。ブクブク太り続けても、「何故この子はこんな体型になってしまったのか」まで考えてくれる人はいない。何か言うとしたら「デブ」と罵るか「やせなさい」と命令するかだ。
本当にずるいことだけれど、この頃から私は、明らかに自分より太っているルミちゃんになつくようになった。
ルミちゃんは高級店で働いていた経歴を持ち、言葉遣いや言うことがすごくはっきりしていた。控え室の女の子たちにもフロントにも、歯に衣着せぬ物言いをするから、みんなに煙たがられていた。顔つきもきつい。
ルミちゃんと仲良くなったわけは誰にも言えない不純なものだったけれど、私はいろいろなことを教えてもらったし、ちょっと世の中を斜めに見たような態度も小気味よくて好きだった。
今日もルミちゃんと並んでお弁当を食べていた。
控え室の中ではみんな一緒に無言でご飯を食べる。テレビや雑誌を眺めながら食べる子や、片膝を立てて食べる子もいる。見ていると、あまり行儀のよい子はいない。No.1、No.2のユカさんとレイコさんだけは、正座して行儀良く、しかも、とても優雅に食べる。
一人の子が、トンカツの入ったお弁当箱を大儀そうに開いた。肘をついたまま箸を使い、一口食べて「まずっ」と顔をしかめた。頬づえをつきながら煮物をつまみ、5分ほどしたら立ち上がった。控え室の隅にある大きなゴミバケツの蓋をあけると、ドサッとお弁当箱を放り込んだ。半分も食べていない。ご飯粒に至っては箸もつけなかった。“残飯”はまだ温かくて、湯気が出ている。
空腹、満腹にかかわらず、食べ物が目の前にあればすぐに手を出していた私は、何ともやりきれない思いでそれを見つめた。
「ああいうの、むかつくよねえ」
ふいにルミちゃんが言った。
「えっ?」
当人に聞こえないかとビクビクしながら、私は思わずルミちゃんを見た。
ルミちゃんは、即即で有名なグループの店にいた時の体験を語った。
「金持っていて旨いものばっか食べているとさ、弁当なんか不味くて受けつけなくなってくるわけ。ああいう女がほんと多いんだよ。だから、私が前にいた店は、自分たちで作らなきゃいけなくなったんだよ。オーナーだかが、女の子がごはん粒に手もつけずに捨てるのを見て怒ったんだってさ。人様にメシを作るよう頼んでおいて、それを箸もつけずに捨てるとは何だ! そんなんなら自分らで作って食え!って。それ以来うちらは当番制でごはんを作っていたんだよ」
びっくりした。個室の中でちゃんと接客さえしていればいいと思っていたけれど、そうではない店もあるらしい。気の休まる時がないじゃないか。
「すごいね。それ、みんなちゃんとやっているの? 文句が出たりしないの?」
「文句もなにも、最初から、あっちの店ではそれが当たり前だもん。個室のセットや片づけの仕事だって、本当に厳しいんだから! だから、高級店で長くやっていると、こういう店に来た時びっくりするよ。タオルのたたみ方ひとつにしてもさあ、うわっ、キタネエ〜なんて思ったもん」
こんなことを決して小声ではないトーンで喋るから、仲間の視線がとても気になっていた。こういう場合でも、私は“聞いていた”とは思われない。“一緒になって悪口を言っていた”ことになるのだ。
新人とはいえ、そんなことはわかる歳だ。私はさりげなく話題をそらした。
考えてみれば、私は控え室でもフロントでも、ものすごく気を遣っていた。
店に在籍の子が多ければ多いほど、人間関係も複雑になってくる。ボーイさんも何人かいて、それぞれが個性豊かだから、「この人がフロントをしている時はキビキビ動かないと怒られる」「この人はすごく敏感だから、ちょっと疲れた顔をしているとやたら心配されてしまう。元気にしてなくちゃ」などと、相手を見て動いていた。
ある意味では、一番神経をとがらせずに済むのはお客の前だった。
どうせみんな、太っていると思っているんでしょ? いいよ、わかっているよ。でも、いいよね? エッチがしたくて来ているんでしょ? ちゃんと、エッチはしたからね。私がこんなことまでしたんだから、何も文句はないよね?という姿勢だ。
容姿も悪く、指名もそう取らない女が堂々と言えることではない。
思うだけならいいだろうと言わんばかりに、どんどん裏表ができていく。
「いらっしゃいませ」とお客を迎える私は、最近笑顔がない。「もう少し痩せたら?」とはっきり言われたあの日以来、この人は本当は今何を考えているのだろうと、それを読みとることに気が向いていた。
たまに「いやぁ、かわいいね」などと言われようものなら、見えすいたお世辞を言いやがって!と、かえって硬い表情になる始末。どんなに優しいお客さんについても、こちらに迎え入れる体勢ができていないからどうしょうもない。
お客と対面した瞬間から、私はその100分後が来るのをひたすら待った。客と別れられる時がお金をもらえる時だ。二人で100分を“過ごす”のではない。私一人が耐え忍び、100分が“過ぎる”のを待つのだ。
控え室に戻れば、当たり障りの内容におとなしく笑顔でいる。誰に指名の声がかかろうが、私が希に指名で呼ばれようが、ノーリアクション。「あの子、あんな体型なのに、どうして?」と思われたくないからだ。
気疲れのせいで帰りの挨拶さえおっくうことがあるけれど、これも我慢して大きな声で「お疲れさまでしたぁ!」と店を出る。「疲れやすいのは太っているせいだ」と、ボーイさんたちにも思われたくないのだ。
今さらのように思うが、完全に心の病気だ。どう考えてもおかしい。
しかし、その時はおかしいことにも気づかなかった。家に帰り、一息つくと、ようやく解放されたと実感できる。緊張から解き放たれた後の間食は実においしかった。ひとしきり食べた後、明日も仕事があることを思い出し、とたんに沈みはじめている気持ちをどう紛らわせていいのかもわからず、そのまま眠った。
公休日も、何もしなくなっていた。何もやる気にならなかった。一日中家に閉じこもって、まるで借金取りから逃れるために居留守しているような休日だった。
これまで生きてきた中で、今が一番容姿の美しさが問われる時。今、一番きれいでいなきゃならないのに。どうして、よりによって今の体重が最大でなければならないのだろう……。
結局、入店して四ヶ月で、体重は5Kg以上増えた。
入店当初よりも接客態度が悪くなっていたと思う。
お客との会話はあくまで時間を稼ぐためだけのもの。体をきっちり洗ってからでないと、一切相手の体に触れられない。マットをした後、お客が「今日はベッドはいいや」と言うのを心待ちにしている。部屋は真っ暗。
入店間もない子があらゆることに抵抗を感じるのは仕方がない。おっかなびっくりの接客、余裕のない態度、そして多少は嫌な思いを我慢していたりもするだろう。これは、経験とともに少しずつ克服していくことだ。
ところが私ときたら、この新人にありがちな至らなさに加えて、コンプレックスの塊みたいになってしまっている。
こんな自分がかわいそうだ。
身のまわりのことがすべて嫌で、しまいにはせっかくの大金を持って帰っても、顔がほころばない。何故みんなこんな大変な世界に飛び込むのかといえば、使い道こそ違えど、目的はお金の一言に尽きる。
曲がりなりにも一応目的は果たしているのに、もうそのことが嬉しくない。どうしてこんなになってしまったのかというと、自分に何の自信も持てなくなってしまったからだ。
けれど、こんな私を誰かかわいそうだと思ってくれないかなぁと情けない期待もしている。
緊張の連続で、どこかがショートしてしまったに違いない。
カンナちゃんは、あまりに短期間で部屋持ちになったため、他の女の子たちにひどいいじめを受けた末に店を移籍したというすごい子だ。
この子ははじめ、控え室はもうこりごりです、と個室待機をしていたらしい。それでも、個室に独りでじっとしていると気が滅入るから、時折フロントに遊びに行ってはボーイさんたちと世間話をしていたようだ。
そのカンナちゃんが、店で見かける私に興味を抱いた。個室待機をやめ控え室に入ろうと決心した頃、ある日私に話しかけてきた。
「お疲れさま。ねえ、私、アイちゃんのこと前から見ていて、この子なら何でも話せそうだと思っていたの。これから控え室でも仲良くしてね」
意外だった。
カンナちゃんは、丸顔の、歳より三つは若く見える美人で、スタイルも素晴らしくて、入店初日から指名客が入るような女の子、どうして私に親しみを感じるのだろう。
けれども、それは嬉しいことでもあったから、私も「よろしく」と言った。
私はもう忘れてしまっていたけれど、カンナちゃんがある日廊下の曲がり角で私と鉢合わせして、ぶつかりそうになったことがあるらしい。
カンナちゃんは仲間の女の子に嫌がらせをされた経験があるから、とっさに「すいません!」と頭を下げるという丁寧な態度をした。
私はびっくりして、「そんな、謝らないでくださいよ〜。こちらこそごめんなさい。あっ、私、アイと言います。よろしくお願いします」と笑顔で言ったのだそうだ。
「アイちゃんが、この業界にしては珍しく普通で、さっぱりしていたから、すごく嬉しかったの。私と同じ丸顔だし」
カンナちゃんは静かに話した。
そんなことで感激するとは、よっぽどそれまでの仲間はひどい連中で、典型的な狐顔だったに違いない。
これを機に、私たちはいろんなことを話すようになった。前の店でひどくいじめられていたことも聞いた。カンナちゃんは私よりも少し年下だけれど、業界歴は一年あり、はっきりしたものの言い方をするから、それだけにお姉さんのような感じがした。
本当に気さくで、自分のことを私にどんどん話してくれたから、カンナちゃんと話している時間は、私にとってはやすらぎだった。
いじめられるなんて考えられなかったけれど、それはひどいものだったらしい。入店三ヶ月でコンドームすべてに穴があけられていたり、サンダルを隠されたり、信じられないような話ばっかりだった。
私は単純な疑問を口にした。
「ねえ、カンナちゃんがどんなに人気者になろうが、いっぱい稼ごうが、周りの子に直接迷惑かけることってないじゃない。自分の稼ぎのことだけ考えていればいいのに、なんでわざわざ手間かけて、嫌がらせするの?」
「アイちゃん、ホント、大好き! アイちゃんみたいな子がもっと周りに増えればいいのに。そうだよ、アイちゃんの言うことって正しいけれど、金津の子って、そういう常識のない子が多いんだよ。久しぶりにマトモな話ができる子見つけた! 私、アイちゃんのまじめなところもすごく好き」
カンナちゃんは私に向かって、よく「好き」を連発した。
それは何だかくすぐったい気分にさせたけれど、心地よくもあった。無条件で相手に受け入れられているという安心感を久しぶりに味わった。
7.やる気
ただ私は、そんなカンナちゃんを遠くに感じてしまうことが度々あった。
カンナちゃんは指名客をたくさん抱える女になりたがっていた。指名をいっぱい取りたい、フリーの客なんかに選ばれる暇がないようになりたい、と何かにつけて堂々と口にしていた。
なるべくお客につきたくない、触られたくない、と思っていた私は、ちょっと面食らってしまった。
ある日、夜遅くにお客についてしまって、早く帰り支度をしなければ、と足早に控え室に戻った。時計は1時を指していて、さすがにもう誰もいなかった。
私は、早く帰り支度をしようと思ったけれど、最前の客でちょっとしたトラブルがあって、そのことを何となく振り返っていた。つっ立ったまま、たまたま視線は壁のグラフのほうに向けていた。控え室には指名の状況がグラフにして掲げてあった。
誰かが来たようで、振り向くとカンナちゃんだった。
「あっ、アイちゃん、今お仕事が終わったところなの」
「うん」
「そうなの。はまっていたんだ」
ハマルとは、最終受付時間ギリギリにお客につくことを言い、その頃には皆帰り支度をしていて、帰れる時間になってから更に一人相手をしなければならないので、否定的な言葉だ。
「グラフを見ていたの?」
私は否定の言葉を出しかけて、考え事の説明をしたくない気分になったから、すぐに返事ができなかった。
「このグラフ、見れば見るほどすごいよねえ」
カンナちゃんが予想外のところへ話を持っていったので、私はまともにグラフに眼の焦点を合わせた。
ユカさんとレイコさんがごぼう抜きのレベルだった。棒グラフは一番上に届き、折り返していた。その長い長い二人の、3分の1ほどの長さの線が次に続いている。それがカンナちゃんの成績だった。後は低レベルで、ドングリの背比べになっていた。
カンナちゃんがグラフの前まで進んできた。そして、ユカさんとレイコさんの成績を示すあたりに指先を向けた。
ユカさんとレイコさんは指名がとても多くて、自分の部屋も持っている。お客さんと夕食をとることがあるのかは知らないが、食事をしに控え室に来ることさえ珍しい。
二人は滅多に姿を見せないだけに、こうしてグラフの結果を見ても、何だかピンと来ない。別世界の出来事のように全く関心を持てない。
控え室にいつもいるメンバーは、似たり寄ったりの指名数で、競争心はないし、指名云々と口に出すのも憚られる雰囲気があった。
何というか、中学や高校で友達同士成績についてあまり話題にしないのと同じだ。誰かの指名数について話題にするって、「いやらしい」ことだった。
だから、こんなにじっくり指名のグラフを見るのはこれが初めてだった。
「すごいよね」
カンナちゃんが呟いた。ユカさんとレイコさんのことだろう。
「そうだよね」
私はあっさり言った。人の指名数にはあんまり関心がなかった。自分の指名もどうでも良かった。そこそこフリー客につくから収入として困ることはなかったし、大体こんな私が指名をたくさん取るなんて無理だし。
でも、カンナちゃんは違っていた。
「いつかは……、いつかは! 私、この二人みたいに、このグラフをピーッとてっぺんまで上げたい」
びっくりした。美人でスタイルも良くて、まだそれほどキャリアもないうちから、それだけ指名が取れていればいいじゃないか。何故そんなに指名にこだわるのだろう。野心家なのだろうか。
カンナちゃんにはそれが当てはまるような気がして、私は言った。
「ねえ、カンナちゃん。私、今までカンナちゃんみたいに、指名されたいとかそんなに思ったことがないんだ。というより、私には無理だと思うんだよね。それに、カンナちゃんは、控え室にいる中では一番指名をとっているじゃない。どうしてそんなに気にするの?」
カンナちゃんは更にマジメな顔になった。
「アイちゃんって、この仕事きらい?」
何だかきらいと言いづらかった。
「う〜ん、あんまり好きじゃないかも…」
控えめに言った。
「あらっ、そんなもの? 私、大嫌いだよ」
びっくりした。とてもホッとしたけれど、それでも何と言ったらいいのかわからない。
カンナちゃんは更に続けた。
「この仕事は、最低で、最高の仕事。でも、誰もエッチなことがしたくて来ているわけじゃないよ。アイちゃんだって、これからたくさん大変な思いをすることは想像できていたでしょ? それでも、お金を貯めたいっていう気持ちが強かったから、こうやって働いているわけでしょ? せっかく割り切ったのに、いつまでもつらい思いをしながら、ただ毎日ヤラレに来るってくやしくない?」
くやしい……そんなふうに思ったことはなかった。太っていてもごめんなさい、でも、お金は置いてってね。お客さんにはそんな気持ちでいた。
でも、考えてみれば、私はくやしいのかもしれない。本当なら値段などつけられる筈のない私の体、私とのセックス、私と過ごす時間。それらすべてに、安くはないものの、きっちり値段がつけられ、現に私はそうして毎日お金を持ち帰っている。
やることをやるくせに、私により一層の要求を押しつけようとするお客も多い。私が懸命につらさを我慢しているのに、自分はしっかり要求を満たして帰る。そういうことがくやしいかもしれないと思った。
「そういえば……くやしいかも。カンナちゃんが言うこととはちょっと違うかもしれないけれど、私、自分にもお客さんにも、いつも腹を立てているかもしれない」
カンナちゃんが頷いた。
「わかるよ。私、今は正直、この人なら楽しく過ごせるなっていうお客さんが何人かいるんだ。でも、決してこの職業が好きなわけじゃないのね。でも、せっかく飛び込んじゃったんだから、“イヤなことをやりにくる”より“すすんで自分の仕事をやりにくる”って思ったほうがよくない? だから私、どうせなら、すっごく稼げるソープ嬢になりたいの。指名バンバン取って、店にも自分の意見がどんどん言えて。私のことを聞くと、誰もが“一度は会ってみたいなぁ”と思うような、そういうソープ嬢になりたいの」
すごい!と思った。カンナちゃんって、すごい。
「お客にイヤなことされるために来るんじゃないの。お金とひき換えに、自分を分けてあげに来るの。高飛車だけれど、こっそり自分の中だけでも、こういうふうに考え方を変えたほうが楽だよ。アイちゃん」
そうかぁ…、何となくだけれど、まだまだ頑張れるかもしれないと思えた。
けれど、指名を取れるようになろうなんて、考えてみたこともなかった。ここ最近、自分の体型を卑下したり、接客がおざなりになったり、何かと逃げ腰だった。でも、指名客を増やすなんて最初から完全に頭になかった。
痩せたい、かわいくなりたいという願望はこのところ強くなってきたけれど、またもう一つ課題が増えるのだろうか。
私はまだ「指名を増やしたい」と言い切ることをためらっていた。
嫌いなお客に、もう一度会いたいと思われることに抵抗がある。そして何より、こんな醜い自分が指名を増やしたいなんて、すごく厚かましい願いの気がする。これはカンナちゃんでも言えない。
とりあえず遠回しに聞いた。
「指名増えたら、仕事楽しくなる?」
カンナちゃんは少し考えた。
「そりゃあ私だって“この人が指名で返ってきた? 何が良かったんだろう。私は合わないと思っていたのに”ってこと、たまにあるよ。でも、初対面の人より全然楽だよ! 手取りも上がるし、自信もつくし、グラフも上がる。私ね、どうせやり始めたこの仕事、徹底的にするために、タトゥーでもいれよかと考えているぐらいなの。とにかく、グラフで目立つ位置にいなければ、こんなつらい仕事、やる意味がないよ」
グラフは別にいいけれど……。私は、足繁く通ってくれるお客というものをまだ良く知らないから、そういう『上客』と『自分に入れ込むストーカー』とを混同している。
言い訳のように返した。
「でもカンナちゃん、皆そんなに指名を取っていなくても、あんまり焦っているように見えないんだけど……」
カンナちゃんは一層真剣な眼になって、グラフに出ている何人かの名を指さし、一段と声のトーンを落として言った。
「この子と、この子と、この人と……。アイちゃん、今のこの人たち、みんな10年働いているんだよ。この子は8年、この子だって5年になるよ」
みんな、そんなにキァリアがあるのか。さぞ仕事にも慣れて、苦労なくチャッチャと百分済ませているんだろうなぁ。私はまだそんな発想しかできていない。
カンナちゃんは続けた。
「ねえ、10年やっていて、本指名が5本も行っていないって、どうなの? この店、そううるさく言わないから、アイちゃんはわからないかもしれない。でも、すっごく恥ずかしいことなんだよ。スタイルもそこそこです、10年選手だからもちろんテクニックもあります。でも、またお世話になろうと思ってくれるお客がいないんだよ! これ、何にも魅力がないですって言っているようなものじゃん。私に言わせれば、こんな子たちは最悪!」
目から鱗が落ちるような気がした。
そうだ、カンナちゃんの言うことは正しい気がする。たまたま指名客が一人来てくれたことでフロントが褒めてくれる今のうちに、頑張らなければ。
「何にも言われんようになったらお終いだよ。ただやられに来て、お金をもらって帰るだけなんて、そんなの“仕事”じゃないじゃん。私はならないよ、そんな女には」
追い打ちをかけるように言った言葉が私の頭に響いた。
ボーイさんが控え室に入ってきた。
「おーい、何やっている。遅いから早く帰ってくれないと、俺たちが帰れないよ」
そして、グラフの前に立ったまま話し込んでいた私たちを見て言った。
「おっ、指名を気にするか。ええことや」
カンナちゃんが、ね!と言うように私を見てニコッと笑った。
単純なものだが、このところ私はとても気分よく仕事をしている。カンナちゃんに認めてもらえたように思えて、気持ちが前向きになったようだ。
そして、カンナちゃんが、また一つ嬉しい話を持ってきてくれた。
「今日フロントに聞かれたよ。以前アイちゃんと遅くまで話していた時のことを」
個室待機していた時の名残か、カンナちゃんは暇な時よくフロントに遊びに行っている。
「フロントの人、言っていたよ。『カンナ〜、アイにいろいろ仕事とか、客のあしらい方とか、教えてやってくれ。仲いいんだろう? あいつ、マジメで性格いいから可愛らしいやろ? ちょっとやる気になれば、売れるんだけれどなぁ』って。わかりましたって、引き受けちゃった」
その後のカンナちゃんの言葉はよく覚えていない。
性格いい、可愛らしい、性格いい、可愛らしい……。
その言葉が頭の中をぐるぐる廻る。褒められた〜〜っ!
カンナちゃんもフロントも、「この子はデブで売れない子」と言わなかったのだ。私を目の前にしたら、真っ先にデブという表現が出てくるはずなのに。それを性格がいい、可愛らしい、身内に褒められたのが嬉しかった。
ボーイさんがそんなふうに思っていたなんて知らなかった。しかも、やる気になれば売れる、と来た。私に可能性までも感じてくれるらしい。
ちょっとした一言なのだろうが、こんなに嫌っていた自分を周りは少しでも認めてくれたことが無性に嬉しかった。
この頃から、店外デートにしつこく誘われたりもあるようになっていた。
私は外で会うようなことまではしなかったが、いろいろな面でお客の言いなりになっていた。電話番号を教えてくれと言われれば、初会の客でも教えていた。電話してよと言われれば、帰った後も眠いのを我慢して電話をかけた。
当然話の内容は「外でも会おうよ」というものになってくる。のらりくらりとかわしながらも、応じる気はないから面倒だ。
一度フロントに聞いてみたことがあった。
「みんな、外で会おうと言ってくるんです。イヤなんですけれど、どうやって断ったらいいんですか?」
ボーイさんは笑って言った。
「アイはバカ正直だからなぁ。ユカやレイコなんか、そんなことはいくらでも乗り越えてきとる。聞いてみい」
そんなことを言われても殆ど会えないのに。
だから、こういう疑問もカンナちゃんにぶつけるようにした。カンナちゃんはよく控え室からお客さんに電話をしている。一度誰かに「○○さん、もう二ヶ月来てくれないじゃないの。そろそろ貢献してくれんといかんでしょ。こっちだってタダで番号教えてやったんじゃないのよ」と、とっても正直に営業していた。
そんなふうに言えるというのがすごい、羨ましい、と思って質問した。
「カンナちゃん、お客さんに外で会おうと言われたらどうしている?」
「何言っとるの。私はあなたとデートするために働きに来ているんじゃないよ。私はここで仕事して、いっぱい指名を取る女になりたいの。邪道なことはしないのよ。そんな私でも応援してくれるなら、また店に遊びに来てね。……って言うよ」
すごい。前にしゃべってくれたようなことをお客さんにもちゃんと言っているんだ。
でも、私がそれを真似ても、何だか似合わない気がする。カンナちゃんも同感だったようだ。
「アイちゃんは、そんなに仕事に情熱を注いでいるタイプには見えないから、実家から通っているって言うとか、妹と住んでいるって言うとか。私も本当は行きたいんだけれど〜なんて素振りは見せちゃだめよ。客は、あきれるほど、外に出やすくするためのアイデアを持ってきちゃうのよ。最終的にははっきり言わないと」
私は、“外で会うなんて考えたこともない子”を演じた。そんな提案をされようものなら、心底驚いた顔をして、「えっ! 外で会わないと、私のこと、嫌いになっちゃうの?」「本当は個室の中では、今まで満足してくれなかったの?」などと、わざとらしい演技をしていた。
8.退店
カンナちゃんは、客としたプレイのこと、自分がイッてしまったこと、本当はマットよりベッドで攻められるほうが好きなことなどをよく話してくれた。
それは結構聞いて恥ずかしい内容だったから、何故こんなに私を信頼してくれるのか怪訝な気持ちにもなったけれど、勉強になったことは確かだ。
「気持ちいい人が来たら、本気で感じちゃえばいいの。楽しい人が来たら、仕事だなんて思わずに、バカ笑いして楽しんじゃえばいいの。そのほうがストレスがたまらないでしょ」
そうかぁ、うん、確かにそうだよなぁ。
カンナちゃんの話を聞くようになってから、今までかたくなに守ろうとしていた自分のルールやお客との壁がどんどん消えていくような気がした。場合によっては、そんなものを取ってしまったほうがいいとわかってきたのだ。
相変わらず、接客の流れはスムーズではなかった。騎乗位が大変だから、できればマットはやりたくない。減りはじめたとはいえ、体重も気になる。
特に何かが変化したわけではないけれど、仕事に行くことがつらいだけではなくなった。何でも話せる子が一人できたというだけなのに。
仕事キライ、今の客キライ、もう帰りたい、こういうネガティブなことを口走っても、それを受け入れてくれる子がいるというだけで、私は本当に救われた気がする。
「あんた、気をつけなよ」
ある日ルミちゃんが小声で言った。
そろそろ年末の繁忙期。カンナちゃんは風邪をひいてここ1週間ほど休んでいる。二本お客が続いて、ようやく控え室に戻り、弁当のふたを開けた時だった。
唐突に言われたことが理解できない。
「気をつけるって、なにを」
ルミちゃんは更に声をひそめて言った。
「カンナちゃんだよ。アンタ最近仲いいじゃん。知っている? あの子、すっごく口軽いんだよ。うちらが何かしゃべっていると、ぜ〜んぶフロントでしゃべっているらしいよ。スパイだってば、あの子」
確かにカンナちゃんはよくフロントに遊びに行っていた。他の子もちょくちょくフロントに行くけれど、カンナちゃんは特に回数が多い。他の店のことは知らないけれど、「こんなに開放的なフロント、そうないぞ。他だったら、控え室にずっといないと怒られるとこだ」とボーイさんが自慢げに言っていたことがあった。
私はそれを覚えていたから、「ただ単に、暇つぶしに立ち寄りやすいだけじゃないの?」と言った。
「ちがうって。あの子が控え室中の子に警戒されているの、アンタ知らないの? で、アンタ仲いいじゃん。アンタらが休みの日にみんなで言っていたんだよ。アイちゃんもカンナちゃんにベッタリだから、控え室のことを片っ端からちくってんじゃないかって」
そんな! そんな理不尽な話が出ているとは、全く知らなかった。
大体、みんなが一つにまとまってワイワイ話すなんてことはなかった気がする。誰と誰が仲がいいとか悪いとか、そういう面倒くさそうなことには興味がなかった。知らなかったというより、見ようともしてなかったと思う。
けれど、私が誰と話し、何をしているか、きちんと見られていることだけはよくわかった。
ルミちゃんには、とりあえず無難なことを言っておいた。
「カンナちゃんとは仲良くしているけど、あの子が控え室の子のことをあれこれ言うのは聞いたことないよ」
本当はそうではない。カンナちゃんは他の子の事情をよく知っていた。悪口を言っているであろうグループの子たちが、何年働いているか、どういう仕事をしているか。
「私は女の子に好かれるタイプでないから、嫌っている人も多い」と言っていたこともあった。
私は聞くだけで、それらの情報を誰かに流すことをしなかったから、話が大きくならなかったのかもしれない。
でも、仲が良くてよく話しているというだけで嫌われるのではたまらない。これから先、カンナちゃんが復帰してきた時にやりにくくなっちゃうじゃないか!と憂鬱になった。
けれど、その必要はなかった。
カンナちゃんが復帰する前に、私は体を壊して休んでしまった。
原因がわからないけれど、ある朝起きたら、顔全体が赤く腫れていた。オレンジの皮のように皮膚全体がぼこぼこと固い。目元も腫れて、鏡を見るのが怖いぐらいだ。全く人相が変わってしまった。
帽子を目深にかぶり医者に行ったが、原因はわからずじまいだった。ただ塗り薬をもらって家で過ごす他はなかった。
全体が熱っぽく、強ばっているため、笑うこともできない。顔の筋肉を動かすと、重い違和感がある。
店に電話をした。顔を見せれば、あっさり休ませてもらえるだろう。それどころか、来ちゃだめと言われること確実だ。
しかし、買い物に行くことさえためらわれるこの顔で、店の人にこれを見られるなんて、とてもじゃないけれどできなかった。
長期休暇は意外なほどあっさりもらえた。無駄遣いしていたわけではないから当面の生活には困らない。いつもソープなんて思っていたほど稼げないと不満を感じていたけれど、こういう時はやはり助かる。OLなんかよりはよっぽど金持ちになっている。急に仕事ができなくなっても、蓄えがあって何とかなる。
私は年末の繁忙期をゆっくり休むことができた。2週間ほどで顔が元通りになった。原因もよくわからないままだった。
一度のんべんだらりとした生活を送ってしまうと、店に戻るのがイヤで仕方なかった。店に行きさえすれば、何万円かは持って帰れる。だけど、どうしても足が向かない。
結局、やっとのことで「明日から行けます」と電話できたのは、もう1週間してからだった。
カンナちゃんが来なくなっていた。
少し見ない間に、何だか店の様子が変わっていた。年末で忙しかったから、控え室でのんびり話す暇もない。そのうちにだんだんわかってきた。
「カンナちゃん、やめたの知っている?」
最初聞いた時は本当に驚いた。今夜あたり泣けてきちゃうだろうなぁと思いながらわけを尋ねた。
「急にどうしたのだろう?」
ルミちゃんが答えた。
「いや、実際急だったもん。姉妹店のほうで働いてくれないかって社長に言われて、その日のうちに荷物をまとめて出ていったよ。でもよかったじゃん。これで、あんたまでがごちゃごちゃ言われることがなくなったから」
もう、そんなことどうだっていい。
「それより、あんたはどうするの?」
聞かれて戸惑った。
「どうするって、なにを?」
ルミちゃんは一気にしゃべった。
「知らないの? ここは即即ありの店になるんだよ。今、店のシステム、どんどん変えていってるみたいだから。即即ができない子たちは、来月か再来月くらいでやめていくみたい。私もやめるけれどね。ここは稼げないし」
そんなこと、何も聞いていないよ。今の仕事をこなせるようになるのだってものすごく大変だった。嫌いなオチンチンを、“ほら、こんなにきれいに洗ったから、全然汚くないよ。大丈夫”と、必死で自分に言い聞かせて咥えてきた。洗う前にセックスして、しかも、その前に咥えるなんて、絶対にできない。
気がつけば、周りの子も雑誌など開いて、移籍先を検討しているようだ。
ここは手取りがいいとか悪いとかしきりに言い合っている。
せっかく慣れてきたのに……。慣れるまでがものすごく長かったくせに、そんなことを思った。
帰り際、フロントに行くと、正月の出勤を求められた。
「大晦日と元日、どっちも八時が最終受付だから、早く帰れるぞ。人数が足りなくて、どっちかは必ず出てくれ」
三週間も休んだという負い目があって、どちらも出ることにした。即即の店になるなんてことは全く話が出てこなかった。
年末年始の客は本当にタチが悪かった。
即即になればやめようと思っていた女の子は私を含めて絶対にやる気が失せていたはずだ。
「きみ、お正月だってのに、予定がないのぉ?」と笑う客。私の予定は、この仕事なんだってば。
「今年初めてのソープで、一年を占うから。きみが良かったら、今年も安泰だ。頼むよ!」とほざく客。自分のことを人に託すな。あぁ、気が重い。
食事の時以外はほとんど休む暇がない。はい次、はい次、と機械的に客についた。はっきり言って、目の前にいるのが誰だろうが知ったことではない。忙しすぎて、目が据わっている。
忙しすぎるわりに、考えることだけはどんどん浮かぶ。
一体私は、何が悲しくて、正月からこんなに働かなければならないのだろう。正月から売春するなんて。
昨日が今日に変わっただけさと、割り切ってしまってもいけない気がした。ここに正月がはさまれなかったら、嫌気がさすこともなかったのかもしれない。
正月があけて二週間ほどであらためて皆が呼び集められ、今後の方針が発表された。
女の子の大半は、即即が義務づけられた時点でやめるつもりでいた。そして、殆どの子が次の店を決めていた。
どうしてそうパッパと動けるのか私にはよくわからない。私は当分ゆっくりするつもりでいた。復帰するかどうかも決めていない。
ソープの仕事の内容は大体わかった。とっても大変だということも併せて知った。自分がやっと覚えたことがムダになるかもしれないという思いはなかった。
男の前で裸になることに加えて、病気、正月の殺人的な忙しさ、そして更に、即即……、次から次へと課せられるものに我慢ができなくなっていた。
どれだけ長く仕事をしても、もう完全にすべてをマスターした、ハイ完璧!ということはないんだなぁ。
控え室を見まわした。皆、旅行先か何かを決めるみたいに、真剣な半面どこか楽しそうだ。
「アイちゃんはどこに行くか決めたぁ?」
話しかけられた。
不思議なのは、これを機にまっとうに働こうと思っている子が一人もいないことだ。今の店で働けなくなったら、次も当然金津園の店という考えにはまだついていけない。
あんなにいろいろなことがあったのに、ちっとも感慨深くない。それどころか、しばらくはせいせいするわと、かえって楽な気分だ。
フロントに、即即まではやりたくないから辞める、と申し出る時が一番怖かった。
けれどフロントは、
「そうかぁ、せっかくいい感じだったのになぁ。でも、次の店でもがんばれよ」
と言っただけだった。
スムーズに退店できることになったのに、スタッフの人にも、すぐ次の店に行くと思われていることがいやだった。
ソープじゃないといけない理由はないんです!
そう言いたかったけれど、黙って最後の仕事をした。
本当にしばらくはゆっくりしよう。復帰するかもしれないし、しないかもしれない。とにかく今は何も決めたくない。
女の子同士、驚くほどあっさりした別れの挨拶をすませ、私は家に帰った。自分のコンドームもボディソープもすべて店に置いてきた。そういうものを家に持ち込みたくなかった。
明日からもう、朝が来るたびに憂鬱な気持ちになることもない。こんなにすっきりした気分になるのは久しぶりだ。
明日は何をしよう……。
多分私は、お客さんの名前も、仕事の内容も、自分がアイちゃんだったことも、きれいに忘れている気がする。久しぶりに普通の女の子に戻れたようで、嬉しい。
何も感じず、何も考えずに、しばらくはリセットすることにしよう。
ソープ嬢をやめた日の夜は、とても幸せな気分で眠ることができた。 (了)
(千戸拾倍 著)