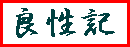
18歳未満の方は入場をご遠慮下さい。
梓 3
梓が四つ年下の由美に入店以来目をかけた。由美に是非入浴するように勧めるから、私は平成三年に由美に入浴した。その時由美は性格が大人になっていないというか、とにかく愛想がなくて、愛撫の技もまるでなっておらず、裏を返す気にはならなかった。
その後、梓が、もう一度由美に入るようにしきりに勧めた。私は平成五年に入って再び由美に会い、とても率直でいじらしいところに心惹かれた。
由美は、親しくなってもいない私に、なかなか本指名もP指名も取れないから容姿に自信が持てなくなった、客に気に入られるように精一杯努力しているけれど、返る客が僅かだからそんな自分がいやになる、どういうふうに仕事をしたら良いのかわからない、控え室で皆と一緒にいるのがつらい、という趣旨の悩みをうち明け、哀しみの表情を表した。
決してコンプレックスなど見せはせず、他人のコンプレックスなら平気でいじる梓ならばありえない行動だった。
私は由美の態度に身震いするほど感動した。それまで私は恵里亜で梓以外の女はほんのつまみとして会う程度だったが、それからは梓の他に由美にも毎月逢うようになった。
由美と親しくなるにつれて、長年通っている梓にはどうにも惚れ甲斐のないところがあると痛感した。
梓は私が来ると馬鹿話にうち興じ、いつも楽しそうに相手をする。豪快に笑いこけ、流し目で悩殺する。でも、個人的なうち明け話や生活ぶりが伝わる話をほとんどせず、梓が心まで裸になっているようには見えなかった。親密さがうわべだけのものに思えた。
梓が私を相談のし甲斐のある男として心の悩みを語ったことは一度もないし、「貴方、素敵な方よ」というような気をそそるセリフを囁くこともなかった。
ベッドの抱擁にしても、梓はエクスタシーにふるえた後、その陶酔をもたらした私に感動して寄り添うような情緒を見せることが殆どなかった。
まだ手淫で決着をつけるようになっていない頃、私は梓と必ず男上位の体位で交合していた。その時、抽送を受ける梓の顔には、甘い表情も、頼るような眼差しも、求めるような表情も浮かばなかった。
シーツの上に伸ばしたままの手を抽送の最中殆ど動かさず、目はたいがい瞑ったままだから、梓はまるで平然と射精を待っているように思えた。射精が迫って梓にしがみついても、梓から迎えるように腰や肩を抱えられることがないのが不満だった。梓の上に乗りかかってする性交はいささか情緒に欠けていると思うことがあった。
梓は逢う度に爆笑を交え愉しそうに喋り、私以外の常連客は何ともつまらぬ男ばかりだ、私と逢うと愉しい、と力説してしなだれかかった。しかし、いざ合体すると、梓には心をとろかすような仕草がないから、私はもう一つ心が完全燃焼できないもの足りなさを漠然と感じた。
でも、梓があまりに美人だから、そのことを愛でておれば良いと思って、不満を拡大することを抑えていた。
梓はベッドに寝てクンニリングスを受ける時も交わる時も必ず頭を枕に乗せた。十代では不良少女だったけれども、そういう所作が示すように、根は慎ましやかな面があった。田舎育ちで存外古風なところがあった。
だから、梓が主体的にサービスをするマットプレイで大胆なことをして男を歓ばせても、男に身をまかすベッドでは奔放な痴態をすることができない気性だということが私は理解できた。
梓は性格も男性的なところがあって、また、露骨な助平話をする割には照れくさがり屋で、とにかくベトベトしたことができない性分なのだ、梓が私にしなだれかかる情緒を期待するな、と諦めていた。
でも、私は由美に通い出すと、抽送を迎える由美の顔に、優しい甘いものが漂っていて、肉体のエクスタシーに精神のエクスタシーが伴うような気がした。
それで、梓に何か一線を引かれている不満を強めるようになった。それにしても、あれだけ親しい間柄なのだから、抱き合うときはもう少し雰囲気を出してくれないものかと思った。
梓にとって私は所詮店の客の一人であることはわかっているけれども、ないものねだりの気持ちが湧かずにはいられなかった。
梓が私に一人の客以上の扱いをしているのかと考えると、商売だと割り切ることができる梓なら、他の常連客にもこれぐらいの愛嬌はふりまいているだろうと思う。また、一方では私以外の客には「お金をくれる射精棒」程度のもっと機械的な扱いをしているような気もする。
若い常連客が友達を連れて遊びに来て、梓の発案で、その友人と相方を部屋に招き入れたことがあった。ベッドと床でそれぞれが交合し、腰の動かしよう、女のよがりようを観察し合ったことを、梓が嬉しそうに報告すると、私は、梓には若い長身の男がやはり楽しくて良いのかと僻んだ。
私に梓がそこまで奔放になってくれるのかしらと、そんな体験をした男が羨ましかった。
由美に通うようになってから半年経った頃、梓が、店の女達が湯浴みをしているところに私を招待して、全裸の女六人で囲んで、ハーレム気分にさせて悦ばせたことがあった。
その時、その二男二女の複数プレイ以上に酔狂な体験を振る舞ったことに私は感謝した。店でも前代未聞の出来事だった。大勢の仲間が裸になってくつろいでいるところに自分の客を案内するなんて、金津園のどこの店でも開闢以来絶対にないことだろう。
大体、店の女達が一緒にシャワーを浴びて、裸で談笑し合うなどということが滅多にない。あったとしても、常連客を連れ込むのを仲間に了解させるのは極めて難しいにちがいない。ポルノ小説の中でのみあり得る特殊な場面設定が、女同士の仲が極めてよい恵里亜の、大姐御の梓だからこそできた。
でも、次に梓に逢った時、梓は「あんなサービスをしてくれるのは、私だけでしょ」と言った。確かに、少々親しくなったぐらいでは誰もそんな破天荒なことは決してしないだろうから、梓の心遣いが本当に嬉しかった。
でも、好意を念押しするなら、「私があんなサービスをするのは、貴方だけよ」と言うべきだ、それを言いながら口づけを迫るぐらいはしても良いのではないか、それぐらいのつきあいと惚れ込み方はしているつもりだと思っていた。
私が熱中する気配を見せた由美よりも自分のほうが豪勢なサービスができるのよ、……そう梓が言いたいのかと、勘ぐりたくなった。あのハーレムの日私の相方は由美なのだが、梓は由美のことをまるで無視しているようだった。
梓の心の中で私はある程度の位置を占めていた筈だ。
控え室で座長になっている梓は皆に私のことをよく話題にしてはしゃいでいた。何かと私のことを喋るから、私の名は店の女の間で有名だった。
「ちょっとみんな、××さんが由美ちゃんのクリちゃんの皮をめくったらねえ、クリトリスの根元が見えたと言ってびっくりしていたわよ。生まれて初めてクリトリスの根元を見た、クリトリスの付け根はああいうふうになっているんだ、と××さんが驚いていたわ。私のクリトリスのカバーはとっても深くって、めくってもクリちゃんの根元が見えないんだって。そう言やー、そうだわ。面白いでしょう。由美ちゃんのお豆の皮はよくめくれるのよ。でも、由美ちゃんのクリトリスの根元を見て驚いている××さんも、とっても面白い人でしょう?」
とても良い男が入って、予想外の技巧で自分が燃焼できると、梓はそれをにたにたとした顔で報告し、私が焼き餅をやいて目をむくのを愉しんでいた。
また、それまでの付き合いが長かっただけに、その付き合いを振り返ってしんみり懐かしむようなこともあったし、私の訪れに間が空けば、なじる言い方もして気にはした。
時には私がはっとするような親密な応対や、他の客には決してしないかもしれない奔放なプレイもした。
「××さん、ストリップしたげようか」
会うなり梓がそう言い、有線の音楽に合わせてベリーダンスのように腰をくねらせながら服を脱いだことがあった。
いつもは衣装棚のそばで手早く服を脱ぐ梓だったが、見事に品をつくって、ゆっくりブラジャーを外し、流し目でショーツを下ろした。片足を高く持ち上げて薄布を取るや、右手を腰に当て、その腰をくねらせながら左手でショーツをふわりと振り回した。
あでやかな本職はだしのストリップショーだった。
「××さん、こういうの、好きなんでしょう。……スケベ!」
妖艶な笑みを浮かべて私を冷やかし悩殺した。
そして、存外にも、いつの間にか自分の乳房の形に関した言葉を口にするようになって、梓が昔と比べれば深く心を許している、と思うこともあった。
実は梓の乳房の形は客ががっかりするぐらい芳しくなかった。
私がまだ二十三歳だった梓と迎賓閣で初会した時、乳房を見て驚いた。若いのに乳房がかなり萎びて垂れていて、それがエトランゼ風の美貌の容姿の中で唯一の欠点だった。それと、開いた膣口のよじれた形からも、梓は経産婦ではないかと想像した。
出産経験について尋ねたかったけれど、しばらく私は我慢し、三、四回指名した頃に、梓に子を産んだことがあるかと尋ねた。すると、想像していた通りだった。十代の出産であったとは意外だったが。
必ず本人はバストの形を気にしているに違いないと思うから、長年の付き合いの間で私は全く一度も梓の乳房を話題にしたことがなかった。バストについての話すら殆どしなかった。
梓に勧められた女に入って、バストがとても美しかったとしても、それを梓に讃えて報告することは控えていた。
「私って下着美人よねえ。ブラジャーをつけると本当にバストの形が良くなるから、下着で男を騙しているみたいだわ」
梓が下着姿で鏡の前でポーズを取って自嘲するように呟いたことがあった。乳房の形が悪いことをちらつかせたのはそのときぐらいで、自分の垂れ乳を直接的に揶揄したり嘆いたりするような言い方をしたことは一度もなかった。
そんな梓がいつの間にか赤裸々に自分の乳房の形を茶化すような風情を見せるようになった。私はそのような梓のちょっとした態度の変化がとても嬉しかった。
梓は難しい仕事をしている恵里亜の女の中でリーダーになって、皆を引っ張り、悩み事の相談にも乗ったり、化粧の指導をしたりして、しっかりした女だった。
新米の女がなかなか客がつかないと、私のような常連客をそそのかして、多少でも指名が稼げるように気を使った。
それだけでなく奔放な言動で控え室の仲間を愉しませた。
客を送って控え室に戻った女の顔を見て、梓が声をかける。
「あんた、さっきのお客でイッたんでしょう。その顔は絶対にイッた顔だ! その顔は、嘘はつけない。孔でイッたの? それとも豆でイッたの? ねえ、どっち?」
梓が部屋の後かたづけをしていると、近くの部屋から妙なるよがり声が流れてきた。
同じ階で客をとっていた由美とリリーも丁度客を送り出したところなので、梓はその二人を誘ってドアの隙間からこっそり中を覗いた。三人は代わる代わる見物してから、笑いをかみ殺して躯を震わせ合った。
その女が控え室に入って来ると皆の前で冷やかした。
「あんた、さっきバックでしていたでしょう。大きなきんたまがあんたの土手にパタンパタンと当たって、いい音してたわよぉ。気持ちよかったぁ、ねえ?……アハハッ、真っ赤になってー」
そんな露骨な会話と剽軽な表情で控え室がぐーっと盛り上がった。
女なら誰でもする仲間への批判や愚痴、そのようなものが梓には殆ど見られず、そのことに私は感心するとともに、逆に、梓が噂話や仲間の欠点批判に興ずる世間並みの女であれば、もう少し可愛げも出てくるのに……と観察していた。
私は、梓と比べれば格段に純真な由美に通うようになると、梓の自分への接し方が段々ともの足りなく思うようになった。
美人の梓との逢瀬に、たとえそれが職業としての密会であっても、私は多少でも何か宙を漂うような情緒を求めたかった。長年、梓を濃厚な愛技で楽しませたつもりだし、数多く会って稼がせもしたのだから、半ば愛人の雰囲気を期待していた。
私は由美に足繁く逢うと共に、梓にも、時には義理を果たすかのように入っていた。
そんなとき、梓が私にロイヤル・ヴィトンから来たばかりのローザという、由美よりも三つ若い女を勧めた。
私は、梓が親切心でそれをしているのか、由美に一種の嫉妬のような心があって、それで、私が気に入るに違いないと見当をつけて、ローザに会うようにそそのかしたのか、疑いの目で見た。
ローザは梓とタイプが異なる美人で、大人っぽい梓に比べ、とことんロリータ風だ。梓が陰をひた隠しした陽性、由美が陽になろうとする陰性とするなら、ローザは根っからの陽性だった。
私は何とも天真爛漫に喋ってばかりいる二十一歳のローザが気に入り、梓と由美に加えてローザにも入浴するようになった。由美やローザが梓より若いから惹かれたのではない。ローザも由美と同様に私のピストン運動を迎える時の表情が艶めかしかった。その感興の違いが大きい。
由美もローザも、私を迎えると他の客とは気持ちの入り方が全く違うと説明した。
何故?と尋ねると、私の情熱的な愛撫のせいだと返した。
「他の人は、誰も、そこまでしてくれないもの」
ローザは前の店からかなりの常連客を引き連れてきた。そんな常連の男に比べて、私は雲泥の差で逢っていて愉しい男だと世辞を言う。
由美とローザは、確かに、私に対しては他の客よりも心を込めた温かい対応をしているのではないかと思わせるものがあった。
逢えば心から嬉しそうに謝辞を言い、楽しそうにブランデーのロックを作った。これからクンニリングスを始める時には、にっこりと微笑んでベッドに横になった。合体しようとすると、気をやってボーっとした顔をほころばせて膝を立てた。
人は誰でもそういう歓待に弱い筈だ。
ところが梓からはそんなことを滅多に感じることがなく、梓が毎度、私の愛技で気をやっても、私が梓を愛撫している間は、梓の強烈なフィンガーテクニックが発揮されていないだけに、私の分身はだらりと垂れていた。
逆に、由美やローザと逢う場合は、部屋に入り裸になって、寄り添って話し合っただけで、それはしばしば力が漲った。私のペニスが一番正直だった。その違いは大きいのに、長年の付き合いの惰性で梓に会っているのかもしれない、と疑問に思うようになった。
迎賓閣から梓を見失ったとき、私は泣いた。年甲斐もなく溜息ばかりついていた。
ソープ嬢がいなくなって涙を流す自分に酔っていたのかもしれない。でも、綺麗で、学識はなくても才知はある、話の面白い梓が本当に好きだった。美貌で繰り出す指さばきと下ネタ話がまさに絶品で、全くエロスの女神に思えた。
梓は青森の出だった。冬は雪で身動きできないような所に生まれ育った女が都会に出て、巧みに化粧をして美貌を輝かせ、男達を惹きつけた。
私は妻子ある身でどこまで梓に惚れ込んでしまうのか自分の心が不安だった。梓が、週一回必ず来る客や必ずダブルかトリプルの時間をとる常連客の話をすると、とにかくその男が羨ましかった。
恵里亜で、思いがけず梓に再会したときのことを思い出す。
梓は昔の常連客の私が突然現れて嬉しがってはいた。私は店に予約を入れたときから、梓がもっと大仰に喜ぶ顔を、廊下にまで響くような声で再会を歓ぶ様をあれこれと思い描き、ほくそ笑んでいた。だから、微笑んだ程度の歓迎はとても残念に思った。
少なくとも梓の常連客の中では、私は相当深い付き合いをしたつもりだし、梓も「客商売」なのだから、もっと私をくすぐる態度を見せてくれたなら、と失望する気持ちをこらえていた。もう、ソープ遊びは止めようかとも思った。
だから、私は胸を躍らせて再会した時の感激が片方向の思い入れだと知ってからは、梓が迎賓閣にいたときのように梓一辺倒にはならずに、同時に、もともと通っていた他の店の女にも続けて会った。
そして、どんなに気に入った女が現れても、必ず他の誰かとも付き合い、それを、自分が恋慕している女に隠しもせず、べた惚れする気持ちが生じないようにしていた。
私は迎賓閣の梓に完全に惚れていた。愛人にすることだけを妄想し、股を拡げてエクスタシーにひたる姿を思い出しては、毎週顔を見るのが難しいことに溜息をついた。恵里亜の梓には、もう、奔放な性技と愉快な会話で私をおだてたりはぐらかしたりして、逢瀬の都度楽しませてくれればいいと考えるようになった。
梓のドライな性格から、梓が恋人のように振る舞うことは望むべきでないとわかっていた。プライベートでもセックスフレンドしかできないタイプの女だ。女らしいなよなよしたイメージはまるでなく、男や家庭との巡り合わせが悪くて片意地に生きている匂いがあった。
それに、ソープ遊びでそのようなことを願うのは、相手が梓に限らず、ないものねだりだ、と自分に言い聞かせた。
私は梓がこよなく愛しかった。深い瞳に妖しい光をたたえ、とろかすような微笑みを見ると痺れた。逢瀬の一挙一動を振り返って、満足感に浸った。
でも時には、梓が随分とすれているように見えもした。所詮、刹那の享楽にのみ興味を持つ浮かれ女だと白けることもあった。
梓に入るのをやめて、由美やローザに絞ってしまったら、いつも顔を合わせる以上気まずいことになるだろうと心配して、もう梓に会うのをよそうと思っていることを由美にそれとなく訴えた。
すると、由美はやんわりなだめた。
「梓さんは言うことが過激で活発に見えても、存外恥ずかしがり屋で内気なところもあるのよ。××さんが好きでも、きっとそのような態度を面に出せないの……」
確かにそうかもしれないが、私は梓がディープキスをしないこと、フェラチオを積極的にしないこと、生のインサートを許さないことの三点が、由美やローザが認めているだけに腹立たしかった。純生のセックスは私のわがままだから別としても、フェラチオやディープキスをするしないは真心の問題と思いたかった。
前年の五月に梓が「××さんはもう事情を知っているでしょうけど、今日からは必ずコンドームを使って下さいね」と求めた。
意外な申し出に、私は、自分がいかにサックが嫌いであるかを力説した。
梓が説教じみた口調で、それが安全のために必要だと説くのを聞いてから、これは、従わなければ駄目だな、と思いながら、私はふざけた悪あがきをした。
怒張したペニスの付け根を指で摘んで、それを上下左右に振り回しながら、風呂場でぴょんぴょん飛び跳ねる飄げたまねをした。
小刻みにジャンプしながら、「純生がいいよぉ。そのほうがずーっと気持ちいいんだよぉ。僕は帽子は被りたくないよぉ。生がいいんだよぉ。……俺が言っているんじゃないよ。息子が言っているんだよぉ!」と子供の声色で叫んだ。
四流コメディアンよりもひどいなぁ、と面映ゆく思いながら、梓を困らせた。
梓の、デパートのおもちゃ売場でだだっ子の無理難題に途方に暮れる母親のような顔を見て、私は、同情と痛快と哀訴と苛立ちと、様々な想いが脳裏を駆けめぐった。
その日私はクンニリングスで梓に気をやらせた後「ゴムつきセックスをするくらいなら、指でこすってもらったほうがいいよ。梓の指の技ならば落とされ甲斐がある」と口をとがらせて言った。
梓は硬い表情でペニスを厳しく揉み込んだ。私は気持ちは複雑なものがあっても、深い射精感で散った。
その後梓は、毎度ベッドの上でもマットプレイのようにローション液をペニスに塗って、華麗な指のテクニックで私をのたうち回らせ、歓喜の悲鳴を上げさせた。
梓が、マットの上で客を俯せにしてテクニックを駆使していると、男はカリ首から棹の幹、アナル、金的のすべてが同時に刺激され、あまりに心地よいので、「お前、一体幾つ手があるんだよぉ。そこらじゅう指先が這っているぜ。まるで千手観音だなぁ!」としきりに感嘆した。
それを男が他の女にも言い、それからは仲間に「千手観音の梓」と冷やかされていた。
梓はそれほどのフィンガーテクニックの持ち主で、私以外にもその手技でフィニッシュして楽しむ客がいた。金津園のソープランドでそれはなかなか聞かない話だった。
しかし、その指先の魔術で射精する快楽は、私にとっては一種の屈辱感さえを伴った。
梓を熱烈なクンニリングスで攻め、梓が粘り気の少ない愛液を流し続けても、感にたえかねて何か甘いことを囁くとか、私の髪や躯に手を差し伸べて撫でたりするような親愛の気持ちがにじみ出る仕草を殆どしなかった。
梓がベッドに両手を置いたまま胸を反らして快感に喘いでいるのを見ると、オーガズムの過程の観察には按配が良いが、私はまるでオナニーを手伝ったような、単に奉仕だけしたような気分になることもあった。
梓との抱擁は、梓がいくら遊び心をくすぐる女でも、男が女を抱く情感が乏しいことに嫌気がさすようになった。
インサートしながら相手の躯を抱えたり熱い接吻をしたりするのは、たとえ「仮初め」と呼ばざるを得ないものでも、互いに刹那の愛情が呼び起こされるものだ。だから、防具をつけてでもきちんとした性交をして、そのような情感のある仕草を求めたいと願いもした。
でも、梓はエクスタシーの陶酔の表情を瞬く間にふだんの顔に戻し、ローションを手にすると、このほうがいいんでしょ、と妖しく眼で会話して、強烈な指技を駆使した。
その都度私は猛爆の射精快感に痺れたけれども、これで満足して良いのかという気持ちはあった。
しかし、手淫を拒んでゴムを着けて梓の肉体に乗っても、梓から求めているような積極的な抱擁、梓が気持ちの昂まりにつれて私の二の腕辺りを無意識に掴むような動作、私を見つめていとおしげに掌で背中を撫で回すような所作、舌を探り合う情熱的なキス、甘い囁きなどのムーディなものは全く期待できなかった。
(そんな心騒ぐ親密な所作をしてくれた女は今までに何人もいたのに。由美もローザも、皆そうだった。勿論、こういうことを期待できない女の数はこの十倍もあったが)
「純生がいいよぉ。そのほうがずーっと気持ちいいんだよぉ」
梓がコンドームを使うように言いだしたときに、私はそんな哀願をしたけれど、梓はすげなく拒否した。こんなことを言わなくても、由美やローザは私への好意の証として、他の客には許していない純生セックスを当然のように受け入れた。
私は梓に、由美やローザとノーサックで性交していることを言わなかった。言いたかったけれど、二人の好意を考えれば秘密にしなければならないと思った。
梓にはゴム付き性交を意地で拒絶し、手淫を愉しんだ。
一度、私がふざけて梓の手に小便をかけて、梓が随分と怒ったことがあった。
マットプレイが済んで梓がシャワーで躯を流している時に、梓にいたずらをしたくなって、いきなり腕を掴み、手の甲にめがけて放尿した。
すると、梓の反応があまりに激しいので、実に意外で、私は白けた。
「あんた、何するのよ。ひどいことをするわね。××さんでなかったら、私、もう帰って!と怒鳴るわよ」
私は、梓が私のアナルの中に指を入れることもするから、不意に小便をかけて、そこまで立腹するとは思ってなかった。
梓は左の内腿に小さな花柄の刺青を入れていた。
私はもともと、梓がどすを利かせた声を出したらかなり迫力があるのではなかろうかと思っていた。梓が赤の他人の悪さを叱るように鋭い眼光を射込み、つかみかからんばかりに激しい口調でまくし立てるとたじろいだ。
それまでの愉快な付き合いは一体何だったのかと思った。梓はやはり普通人とは異なる蔭の世界の連中と縁がある生活をしていたのではないか、と疑う気持ちが生ずるのが残念だった。
私を送り出して控え室に戻ってからも、梓は大層な剣幕でいつまでも怒っていた。
「ちょっと由美ちゃん、××さんって、とんでもないことを私にしたわよ。私、あの人があんなことをする人だなんて、全然思ってもみなかったわ。ちょっと聞いてよ。本当にひどいことを黙ってしたのよ。『ちょっとそばに来てよ』と言って、何かと思ったら私の手を掴んで、その手に、あの人、何も言わずにいきなりおしっこをひっかけたのよ。私、あの人は紳士だと思っていたのに」
由美は梓のあまりの剣幕に、私との間のことならそんなに腹を立てなくても良いじゃないかとおかしがった。そして、梓のしつこい繰り返しと怒りの表情の中に、梓が私のいたずらの意外性を愉しんでいるような痴話喧嘩を感じたようだ。
由美が私の指名を受けて控え室を出ようとする時、梓が由美に声をかけたことがあった。
「ちょっと由美ちゃん、次の客は××さんで、今月××さんは二回目でしょう? 私は一回だけよ!」
由美は、梓がパソコンの予約表を調べていることに驚いた。
その頃梓は何かの折に、「××さんって、本当に律儀だわ。よく飽きないで私のところへ来るわねえ。本当に長い付き合いよ。……」と呟いた。
ソープの常連の客には二年三年続けて通う男も中にはいる。しかし、大部分の常連客は三ヶ月から一年ぐらい続いて、それで現れなくなるのが普通だ。料金は払うに楽な額ではないし、第一、金津園には女がいくらでもいる。眼が移るのが当たり前だ。
三ヶ月や一年というような短い期間ではない年数を追っかけた私に、梓が「律儀」と言ったとき、感謝や感動の気持ちよりは、何か揶揄めいたものがありはしないか、と私は梓の瞳の裏を覗いていた。
私は由美もローザも通うようになっても、二人とも梓が勧めた女だから、(私がいる店の、私が勧めた女に乗り換えたのね)と梓に思わせるのが嫌で、止めてしまうのを思いあぐねていた。やはり私は梓が好きだった。
いつぞや、恵里亜の女が四人ばかり風呂に入っていた部屋に私を案内して、ハーレム体験をさせた梓のサービス精神や、私がローザと逢っているときに部屋まで覗きに来て、ローザには全く言葉をかけず、馴れ親しんだ口ぶりで私を冷やかす親愛のポーズがその都度私を押し止めた。
梓はローザの部屋でくつろいでいる私を刺すように見つめて冷やかした。
梓のメーキャップをしっかり仕上げた顔を眺めると、私は、ローザも良い女だけれど、やっぱり自分はこの女の虜かな、と思ったりした。
好きで好きでたまらないけれど、惚れ甲斐のない梓は今回で最後にしようかどうしようかと悩む逢瀬がしばらく続いたのだった。
更にその後、私は夏美にも通うようになった。
初会の時には、全く無愛想で、サービスのかけらもなく、容姿も平凡で、それほど若くもなく、どうしょうもない奴だとあきれ返り、即物的な射精で終わった。
それから二年後に東京ディズニーランドへ行く梓の一行に夏美もいて、私が梓と談笑していると、夏美が胡散くさげににらんだ。その仏頂面には白けた。
でも、その二ヶ月後に、たまたま夏美に再度入浴することになった。夏美が初めてのオーガズムに陶然と乱れて、仄かに好意を見せると嬉しくなり、それから一ヶ月間で三度も夏美と逢った。
私は痺れるような交歓プレイをして、夏美に徹底的に淫蕩教育をした。
夏美は見事に誘導に乗った。私の情熱の愛撫に、淫らに股ぐらを開けっぱなしにして快感にゆれる好色反応を返した。よがり汁をだらだら流して性の快楽に身をまかせ、陶酔の表情を見せるから私は亢奮の極みだった。
堪えぬことができない風情のよがり声を上げ、なかなかエクスタシーが深くて、気をそそられることがこの上もない。それだけでなく、射精した後、精液を垂らす膣口がいつも丸く開いてとてもエロっぽい。
とにかく夏美が他の客には見せることのない好意的な態度で迫るから、これまたぞっこんになってしまった。
すっかり親しくなった夏美に梓とはいつも手淫で空中発射していると教えると、夏美が「あれま、気の毒!」と驚いた。
その一言が、そのあきれた表情が、俺は気の毒な男かと思う気持ちが、あらためて梓に通うことの意義を考えさせた。
梓が純生のセックスに応じないから、依怙地になって梓に一年半も手淫をさせたのかもしれない、そんな男は日本中探したって自分しかいないに違いない。
夏美は長年金津園で働いているのに、客の前で股を開くこと以外は何もしなかった。そのサービス精神の全くない夏美に、私はペニスの刺激の仕方を中心に、ソープ嬢が身につけるべき愛撫のしかたを教え、夏美は熱心に私のセックス指導についてきた。
意外なことに、指や掌を私の感受性の高いペニスにしつこく這わせたり、吸いしゃぶるような生のフェラチオで激しく勃起させる愉しみを理解し、更にはカリ首を両手で揉みながら尻の穴をしっかり舐めるまでになった。
夏美は、私以外の客には、ゴム尺ではあるけれど真面目にフェラチオをするように接客態度を変えた。でも、そこらの男にはディープキスや生のフェラチオやアナル舐めを絶対にしない、と嬉しいことを言った。
男の気をそそるようなことを全くしなかった女が、ディープキスを交わしながらヘビーペッティングを受けたり、玉しゃぶりもアナル舐めも熱烈にするようになったその心の入れ替え方が可愛い。私が愉悦のうめき声を上げるのを愉しむようになって、好意を隠そうとしないのが嬉しい。
夏美が思いの他親密に応対し、すっかり淫奔な女に変身してしまうのを見て、もう梓に通うのをやめる潮時だと思わずにはいられなかった。
梓、由美、ローザ、夏美と、恵里亜で四人も馴染みの女を作っているわけにはいかない。
由美もローザも夏美も私には他の客と違う格別の好意を寄せた。金津園でコンドームの使用が定着してから通うようになったのに、その三人はコンドームなしで合体を許した。私が抽送しながらディープキスを求めると唾液が絡むまで唇と舌の応答をしっかり返した。
梓は、クンニリングスで気をやらせた後に私が唇を寄せると、「わぁー、おまんφくさい。いやー!」と大声を出して顔を背けた。
本当に自分の愛液の匂いがイヤなのか、ディープキスそのものがイヤなのか、と考えるとむしろ後者だった。
心のこもったキスはプライベートラブでしかしないという主義なのか、キスそのものがイヤなのか、と検討すると、やはりこれも後者だと思う。
キスを嫌うソープ嬢はいるものだし、私の歯が煙草のヤニで汚かった。だから、梓がキスを嫌がっても、迎賓閣ではそれほど気にならなかった。そんなことを気にして惚れている気持ちを揺るがしたくなかった。
でも由美は、私が通うようになると、ムーディにディープキスを受け入れただけでなく、私が、梓がディープキスをしないことをぼやくと、梓の固い態度について非難めいたことを呟いた。
それで、私は梓が熱いキスをしないことを奥歯に挟まった野沢菜のように強く意識するようになった。
ローザや夏美が口唇愛撫で気をやった後にキスをすると、その二人のよがり汁の匂いが由美よりも一段と濃いので、私の口許から発する淫汁の妖気が互いの顔の間に立ちこめた。私はいつもその匂いに痺れた。
そして、唇を離すと、ローザも夏美も同じことを言った。
「むちゃくちゃ、おまんφのにおいがしたぁ!」
ペニスを膣道に嵌め入れながら笑顔で呟く顔を見て、私は、梓の眉をひそめて顔を背ける拒絶を思い出し、舌打ちした。
三人とも、心からのディープキスをして、逢えば、私が来るのが待ち遠しかったという気持ちを面に表した。皆、ディープキスやアナル舐めなどの大胆な閨房の技について「こんなことをするの、××さんのときだけ」と笑顔で言った。
それは、お愛想もあるかもしれないが、本音だろうと思った。歓心を買おうとするような微笑みは恋愛遊戯をしたい私の願望にかなうものだった。
梓はその三人と比べれば断然付き合いが長いけれども、私にそれほど別格の応対をしているとは思えなかった。
夏美が梓について二つの興味深いことを語った。
「二輪車をしてお客さんが女の子にレズ行為を求めることがよくあるけれど、女はその趣味がない限り、女のあそこを舐めるのはとっても嫌なのよ。だって、何だかとっても汚く思えるもの。男の人のあそこにはそんなことを全然思わないのに。でもね、梓さんね、ローザちゃんとコンビで二輪車をして、お客に二人がレスビアンをするように求められて、そのときにローザちゃんをイカしたんだって。ローザちゃんから聞いたわよ。とっても上手で、ローザちゃんはあっという間にイカされたんだって。梓さんは結構レスビアンの経験があるみたいよ」
「××さん、部屋の戸の下のほうに隙間があるでしょ。梓さんね、あそこから部屋の中を覗く趣味があるのよ。何だかいろんなことを知っているので変だなと思っていたら、私、あの子が腰を屈めて人の部屋を覗いているところを見ちゃったの。すごい子でしょ。言っちゃ駄目よ。
でも、私も覗いたことがあるの。だけど、変な気持ちで見たんじゃないのよ。廊下にいたら、女のちょっと不審な声がしたの。ひどいことをお客にされているのでは、と心配して覗いたのよ。そうしたらリサちゃんがね、すごい格好でよがっていたの。私、びっくりしたわ。お客も彼女もベッドに座って、彼女が扉のほうに向かって大きく股を開き、男の人が右手であそこをさわっているの。彼女、わぁーわぁーと派手に声を上げて、おちんちん握ってそり返っちゃったりして、ものすごく猥褻なポーズだったわ。
リサちゃんが、私に『見て、見て!』というような姿で、もう丸見えで、いかにも気持ち良さそうな顔をしていたから、私、覗いていてすっかり亢奮しちゃった。まるで、私に見せつけるみたいだったわ。私、リサちゃんに危ないことでもあったんじゃないかと、本当に心配して覗いたのよ。……梓ちゃんは、仲間同士であそこを比べ合ったり、覗きをしたり、本当に助平なのよ。でも、私も助平。私、男と女が一生懸命やっているのを側で見ていたい!」
夏美は途中までは悪戯っぽい顔つきで喋っていたが、そのうち、私を引きずり込む目つきになった。
ちょっと前にローザが「××さん、上手だけど、女が女の人を攻めたらもっと上手よ」と言うので、私はおやっ?と思ったことがあったが、ローザが梓にイカされたと聞いて納得した。
私は久し振りに梓に会った。
マットプレイが済んだ後、梓に、ローザとのレズプレイのことを確認した。
「えーっ、誰に聞いたの。でも、ローザちゃんに舌を使ったんじゃないわよ。指だけよ。私、女のあそこを舐める勇気ないわ。ねえ、誰に聞いたのよぉ?」
「この店の誰かだよ。指にしても、さっとイカせるなんて、さすが梓だね」
「私、この店の子で、もう一人イカせたのいるのよ」
「へーぇ、誰?」
「リサちゃんよ。内緒よ」
「その子もやはり指だけかよ?」
「そうよ。でも、あの子に聞いたら、あの子も私をイカしたと言うかもしれないわ」
喋る梓の笑顔が何となく妙だった。
「ん? お前、イッたふりをしたんだろう?」
「うふっ、そうなのー。内緒よぉ」
「リサっていうのは助平そうだな。一七〇センチぐらいの、背の随分と高い子だろ。僕に合いそうかい?」
「ちょっとちんぴらぽいから、××さん、タイプじゃないわ」
「ふーん、不良じみたのとか、すれた感じの女は、僕は絶対に嫌だからなあ。でも、あんた、女の子に人気があるから、みんなにレズをやってあげたら喜ぶぜ。梓とレズをやりたい女はきっといっぱいいる。顔は綺麗だし、服のセンスはいいし、頭はいいし、とんちはあるし、いろいろと仲間に気を使って思いやりがあるし、普通、皆が言わないような、核心を突いた、人の心をえぐるようなきついことを、平気でずけずけ言うし、その割にはそれほど恨まれないし」
「ふふっ」
そんな会話の後、私は梓に、由美やローザや、先月から通うようになった夏美の三人が濃厚なキスと熱烈な愛撫をして、いかに心を揺さぶる親身な応対をしてくれるかを語った。夏美の名前は伏せた。
梓は、私が由美とローザの二人に通っていることを知っていた。更にもう一人女が加わり、女に何かと期待する私がその気になるほどサービスが過激なようだとわかると、盛んに新顔の名を聞きたがった。
私が、よほど気に入らないと同じ女に二度三度と入らない男だと知っていたし、店の売れている女には一通り会って悉くくさしたから、私が歓ぶほど高度な愛撫の技巧を身につけ、気をそそるような女がまだ恵里亜に残っていたのかと梓は不審だった。
「一体その子、誰なのよぉ。言いなさい。(指名を)二十本取る子なの?」
「同じ店だからいずれわかるよ」
「要するに助平な女なんでしょ。本当に貴方は助平なのが好きなんだからぁ」
「……」
「でも、何だかんだと言って、また××さんはしばらくすると、ちゃんと私のところへ来るの。××さん、大分前に由美ちゃんに、もう私のところに来るのをよそうかと相談したんでしょう?」
「うん」
「で、今日来ているじゃない」
「いや、今度は最後かもしれない。ハートを揺すられるのは、何と言ってもいいことだから」
「でも、最近は演技が上手な子がいるのよねえ。古い子でも、××さんがよく来る人だって知っていれば、何とかものにしようとしたのかもよ。ローザちゃんなんか、今この店のナンバーワンなのよ、知ってる? 話が上手いんだからぁ」
(本当に梓とは長い付き合いだったなぁ。『最近は演技が上手な子がいるのよ』というのは、ローザのことを言っているのかな?)
「演技でも打算でもどっちでもいいの。そういうふうに演技してでも僕を捕らまえようとするのは、僕にとっては二番目にいいんだ。僕にちょっぴり惚れちゃってそうするなら、一番目にいいの。いずれにしても何も気持ちを面に出さない女よりいい。そのような雰囲気を全く見せてくれない君よりそっちのほうが男は痺れるんだぜ」
私は貧乏揺すりをしながら梓から視線を離して喋っていた。
(梓は、私の言葉を惜別の辞と理解して聞いているのだろうか?)
その日私が梓に予約を入れたのは、(梓は今度こそ最後にする。別れの対面をして、その辺を仄めかしておこう)と思ったからだった。
何故かその日は部屋に入ってからその時まで、私はマットで俯せの姿勢のとき以外は、ずーっと梓の顔を見続けていたような気がした。
梓は全裸のまま横着に床置きのエアコンの上に尻を下ろしていた。最前のマットプレイで火照った躯を送風口からの換気の風で冷ましながら、タオルを振って顔にも風を送っている。
床にあぐら座りをした私を見下ろして梓が話しかけた。
「私、昨日プライベートで猛烈なセックスをして、ヒィヒィ言っていたのよ。ものすごく気持ち良くって、完璧にダウンしたから、今日はイケるかなぁ。昨日の男はとっても良かったわよ。延々とセックスしてた。好みの男だったから。私だってプライベートにセックスをする男がいるのよ」
胸を張り肩を小揺すりして喋る顔つきが、小生意気で、悪魔的な妖しさを漂わせていた。
梓らしい言葉でもその日ばかりは白けて聞こえ、私は、梓のその挑発に何も言葉を返さなかった。
そんな話題ならば交合の具体的な様子を尋ね、梓に卑猥な描写をさせて、何か冷やかしたりするのが普段の私だ。ところが、無視して何の反応も返さなかったので、梓は戸惑ったのが眼に現れた。
梓が無言を恐れるように、続けて何か喋っていた。
私はブランデーを飲みながら、別のことを考えていた。
(去年までは一店一人にできるだけ絞ろうとしていたけれど、梓のお蔭で今年に入ってそれが崩れてしまったなぁ。由美もローザも夏美も、皆、こいつの勧めがきっかけで通ってしまった。でも、こんな猛烈な放蕩はなかなか面白いものだ。……しかし、梓のこの格好は実に絵になるなぁ。由美やローザや夏美なら、素っ裸で行儀悪くエアコンに腰かけて、友達のような馴れ馴れしい喋り方はしないだろうが。……萎びたおっぱい以外はむちゃくちゃきれいだぜ)
梓は両手を揃えて投げだし、くの字になったまま背中を私のほうに向けていた。
(千戸拾倍 著)